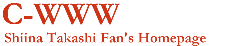2007/08/18
■マンガ版ノアの方舟計画
いわばマンガの「ノアの方舟」ですね。
各自残す条件は様々あるかと思いますが、フジモリの条件としては以下のとおり。
「三軒茶屋 別館」のフジモリさんが書かれた記事。前に私が書いた引っ越し時のマンガ選別ネタを元に、更に踏み込んだ考察をされています。
「このマンガの存在は今の自分の人格を構成する要素になっているか?」という自分が書いた漠然とした判断基準を、より明確な形で条文化してくれた、という印象です。こうして書かれてみると、自分の場合は「神格性」「常習性」「根本性」をより重視して本を選択しているように思えます。自分の好みが可視化された感じがして面白いですね。
話題として取り上げて下さり、ありがとうございました。
なお本の選別については、本屋で売ってるコミック以上に、これまで即売会で買った同人誌の選別作業の方が、遙かに心理的に厳しかったことを申し加えておきます(笑)。同人誌は希少性が高いので、こういう時はホント処分に困ります。
2007/08/12
■漫画ナツ100に参加します
本棚リストを元に、「酔拳の王 だんげの方」さんが開催している漫画ナツ100用の漫画推薦リストを作りました。
下記のリンク先が、漫画一覧を書いたテキストファイルになっています。5つ目のフィールドに入っている文字列は、対象の漫画のコミックス1巻のISBN(ISBNがないものはAmazonのASIN)です。
よろしくお願いします>だんげさん。
この中で微妙なのが掲載されている作品の大半が週刊少年ジャンプに掲載された「七つの海」、および週刊少年サンデーに掲載された「暁の歌」なのですが、これは全て読み切りの短編であり、定期的に「連載」されていた訳ではないので、一応ここに入れておきました。もし問題があるなら除外して下さい。
今回のレギュレーションだと、トップに来るのは「よつばと!」か「シグルイ」になりそうな予感。
■引っ越し後の本棚リストを公開したくなった(1980年代以前版)
本棚晒しエントリ最終回。1980年代以前の古い本です。
高橋留美子と藤子不二雄がホント好きだったんだなあ自分。
1980年代
- ラプラスの魔 (MEIMU, 1989年)
- 同名のゲームのコミカライズ版。ただしゲームとは趣が異なり、主人公のミーナ達が館を探検するうちに様々な物語の世界に入り込んでしまう、という形で物語が進んで行く。「ラプラスの魔」というネームバリューのある原作に対して大胆にアレンジを施したことが印象に残っているマンガ。この頃のMEIMU先生の個性的な絵柄も魅力。
- ロマンシア―浪漫境伝説 (寺田 憲史/円 英智, 1988年)
- これも同名のゲームのコミカライズ版。この頃はパソコンでゲームばっかりやってました(自分語り)。
ただ、ゲームの方はさらわれたお姫さまを助ける王子が主人公なのだが、マンガの方は主人公の女の子が王子を助けるために旅に出るという形になっている。内容も激しくアレンジされていて原作の跡形は微塵もないんだけど、これも原作の制約を外したことで逆に面白くなったタイプのマンガだと思う。あとマジシンがかわいい。褐色少年萌え。 - バオー来訪者 (荒木 飛呂彦, 1985年)
- 「
そいつに触れることは死を意味するッ!
」という特徴的なアオリが今も語り継がれる、荒木飛呂彦先生の初期の傑作。これが打ち切りを食らったマンガだとは思えない程の高い完成度を持つ。当時リアルタイムで読んで衝撃を受けた作品。 - るーみっくわーるど (高橋 留美子, 1984年)
- 高橋留美子先生の短編集。この時代までの高橋先生作品のエッセンスを結集したような本。中学生時代に愛読していた記念として保存してあります。
- めぞん一刻 (高橋 留美子, 1982年)
- 近代恋愛マンガの礎。これも中~高校生時代にリアルタイムで読んでいたので保存。
一つの連載を最初から最後まで追いかけ、リアルタイムで友達と盛り上がることの面白さを知ったマンガでした。 - つくろう!同人誌 (まんがカレッジ, 1983年)
- まんカレ謹製の同人誌作成マニュアル。同人誌と言っても二次創作同人とか面妖本とかそういうのではなく、純粋にオリジナルのマンガを書いて同人誌を作ろう! でもって小学館の同人誌グランプリに応募しよう! という趣向。そんなのあったんだ昔。
マンガ好きな男子が仲間を集めて同人誌を作る、という筋書きの本なのだが、その男子自身はマンガを描かないで編集に専念するというのが、この手の本としては珍しいような気がする。マンガや本を制作するにあたっての基本的な知識を教えてもらった本として個人的には思い出深い。 - ダストスパート! (高橋 留美子, 1980年)
- 「るーみっくわーるど」には掲載されていない「儲かり末世」が掲載されている貴重なコミックなので保存。残し方が微妙だ。
昔ブックオフで100円で買った記憶があります。ブックオフはたまにこういう本が流れているので油断できない。
1970年代
- オリンポスのポロン (吾妻 ひでお, 1979年)
- 子供の頃は、よく姉の部屋に忍び込んで姉が買ってた「月刊プリンセス」をこっそり読んでいたものですが、その中で一番好きだったのが「オリンポスのポロン」でした。小学生時代の思い出の作品として保存。姉ちゃんごめん。
- T・Pぼん (藤子 不二雄, 1979年)
- 潮出版社版を所有。藤子不二雄先生のSFマンガにハマっていた頃にこのマンガの存在を知り、「主人公がタイムパトロールになって歴史に埋もれて非業の死を遂げた人を救う」というロマン溢れる内容にすっかりメロメロに。あと、主人公の先輩格のリーム・ストリームにもメロメロに。
「のび太の恐竜リメイク版にリーム姉さんが出て来ないのは許せねえ!
」とか言ってる困った人は、みんな子供の頃にこれを読んでリーム姉さんに萌え萌えになってたオッサンです。人のこと言えませんが。 - エスパー魔美 (藤子 不二雄, 1978年)
- てんとう虫コミックス版を何巻か所有していたが、痛みが激しいため小学館コロコロ文庫版のみを保存。これなしではオレの厨時代は語れないぜ! みたいな位置付けにあるマンガ。
このマンガの最大の価値は、主人公の超能力者に適切な助言を与える「高畑さん」という概念を発明したことにあると思う。あと、そういうポジションにいるキャラをあえておっさん体型にしたのも凄いと思う。オレはあの頃、高畑さんになりたかったんだ…(厨っぽく) - 異色短編集 (藤子 不二雄, 1977年)
- 宇宙人 (藤子 不二雄, 1979年)
- 「異色短編集」は小学館から出ていた藤子不二雄先生のSF短編集。「ミノタウロスの皿」「劇画・オバQ」「ウルトラスーパーデラックスマン」「ノスタル爺」などが収録されている全6巻のコミックス。「宇宙人」は朝日ソノラマから出ていたSF短編集で、「宇宙人」「ぼくは神様」「みどりの守り神」などが収録。
この辺はもう自分の一部になっているので手放せません。大事に持っていたいと思います。
2007/08/10
■引っ越し後の本棚リストを公開したくなった(1990-1994年版)
お久しぶりです。前回の俺様本棚語りの続きです。
今回は1990年~1994年のコミックを羅列。そろそろこの辺から10代の方は置いてきぼり気味になります。
1994年
- Aquarium (須藤 真澄)
- 新声社版を所有。須藤真澄先生のマンガをちゃんと読んだのは多分これが初めてだったと思う。輪廻の概念と水族館を組み合わせたユニークな世界観と、ほのぼのな雰囲気ながらも「生命」について考えさせられる懐の深さも持った作品。
あと、これ読むと水族館に行きたくなること請け合い。当時はこのマンガに触発されて池袋のサンシャイン水族館へ行き、マンボウをずっと眺めていたモノでした。懐かしいなあ(自分語り開始)。 - 覚悟のススメ (山口貴由)
- もはや、自分にとってのバイブル的な存在のマンガの一つ。作者の熱意が絵や台詞から迸りまくっている、文句なしの傑作。当時は、山口貴由先生とはこのマンガを描くためにマンガ家になる運命を授けられた存在に違いない! と思い込んでいた程(迷惑)。
「シグルイ
」もそうですけど、山口先生のマンガは「山口貴由でなければこのマンガは絶対に作れない」と感じさせる強烈な個性を感じさせます。
1993年
- 海底人類アンチョビー (安永 航一郎)
- 基本的には(この時代における)いつもの安永航一郎先生のマンガなんだけど、最終巻ではいきなりハードSF的な展開を見せるところが侮れない。そんな中でも話のノリは相変わらずの安永節なところも凄い。何かこう安永先生のマンガ家としての地力を見たような気がする、という意味で印象的なマンガ。
- エンジェリックゲーム (柴堂 恭子)
- 柴堂恭子先生のマンガとしては珍しい、現代(1990年代)を舞台にしたサスペンスドラマ。物語後半では当時自衛隊が派遣されたことで話題になっていたカンボジアを舞台にするなどの意欲作ではあったものの、何かよく判らないけど諸般の事情で未完扱い。どうした小学館。
個人的にこのマンガが記憶に残っているのは、多分柴堂恭子作品としては(これも)珍しく男女の恋愛を真正面から扱っている話だったからと思う。 - ダンジョン・マスター (栗橋 伸祐)
- 同名のゲームのコミカライズ。原作のゲーム世界の設定を尊重した上で、パーティーのキャラクター達(全て原作のゲームに登場する)にこのマンガ特有の個性を付けることに成功している。ゲーム原作のマンガとして、とてもよくできている作品だと思う。
- コーリング (岡野 玲子)
- 潮出版社版を所有。ファンタジーの名作「妖女サイベルの呼び声」のコミック版。岡野玲子先生の卓越した表現力によって、作品世界を更に魅力的なものとして描いている。またストーリーの面でも、重要なシーンでは原作にない心理描写的な掘り下げがなされており、原作を事前に読んでいれば更に楽しめるようになっているのも素晴らしい。祖父江慎氏による「魔術書」っぽい装丁もステキ。本棚に常に飾っておきたい本。
- がらくた屋まん太 (能田 達規)
- 自分が初めて能田達規先生の存在を知ったマンガ。主人公が様々な発明品を作ってご町内を舞台に大暴れするという、後の「おまかせ!ピース電器店」の礎となる痛快ハチャメチャガジェットSF。終盤になるとシリアスな話が増えるものの、基本的にはウィットとSFマインドに富んだユーモア溢れるギャグマンガ。今読んでも面白いです。にしても中古価格が高いなあ。
1992年
- グリーンゲイトへようこそ (めるへんめーかー)
- 我々の世代にはファンタジー漫画の旗手としてなじみ深い、めるへんめーかー先生の作品集。イギリスの田園都市を舞台にした、全体的にほのぼのした雰囲気のコミック。青春時代の思い出として保存。こういうの好きなんですよ。
- マトゥルスの血族 (沢田 一)
- 最近になって完全版が出て個人的にビックリしている、沢田一先生の初期の作品。ドラゴンマガジンで連載。冒頭はこの時代のファンタジー作品に頻繁に見られる「乱暴な主人公男子と気の強い女子」の冒険行な話なのだが、「不死」を題材に徐々に物語のスケールがアップして行く展開の力強さが魅力。あと、最初に敵役として出てくるキーラ(属性・ツンデレブラコン女子)がモリモリ可愛くなっていく様が萌え。
- 七つの海 (岩泉 舞)
- 今も根強いファンを持つ、岩泉舞先生の現在唯一の作品集。気弱な少年の心の成長を描いた表題作の「七つの海」、世界から徐々に忘れられ消滅していく主人公の心情を描いた「ふろん」など、今もその内容を鮮明に思い出せるくらい強烈なイメージを自分に残しているマンガが掲載。これからも決してその存在を忘れないであろう本。
- GS美神極楽大作戦!! (椎名 高志)
- 結果的に、これと出会ったことで自分の運命が変わってしまったマンガ。当時は、本気で「美神令子みたいになりたい」と思ってました。いや別にワンレンボディコンの姉ちゃんになりたかった訳ではなく、自分の力だけで自信を持って好きなように人生を渡り歩いていけるくらい「強い」人間になりたい、という意味でです。ホントです。
一番好きな女性キャラは小鳩ちゃんです(聞いてない)。
1990-1991年
- 燃えよペン (島本 和彦)
- 竹書房版を所有。「燃える漫画家」島本和彦先生の、言わずと知れた名作。「
時間が人を左右するのではない! 人が時間を左右するのだ!
」等、魂を揺さぶられる至極の名言の宝庫でもある。漫画家志望に限らず、何らかの大望を志している人は読むべき。 - 巨乳ハンター (安永 航一郎)
- 安永航一郎先生の魅力が凝縮しているギャグマンガ。おっぱいとかが沢山出てくる不健全な内容にも関わらずどこまでも健康的な雰囲気、清々しいまでに徹底された馬鹿馬鹿しいストーリーの数々、B級的な意味でのパロディセンスの素晴らしさ。全てが上手く噛み合った作品だと思う。
- グラン・ローヴァ物語 (柴堂 恭子)
- 潮出版社版を所有。初期の柴堂恭子先生作品にして、柴堂作品の魅力が凝縮して込められているようなマンガ。読むと「世界」や世の生き物たちに対する考え方が変わるかも知れない――と言っても過言ではない、ファンタジーならではの壮大なスケール感を持った作品。
あとイリューシアかわいい。超かわいい。自分が人外萌えに目覚めた作品でもあります。 - 伝染(うつ)るんです。 (吉田 戦車)
- 言わずと知れた四コママンガの革命的存在。よって説明不要。これは持っとかないと。
- キャウ・キャット・キャン (道原 かつみ)
- SF的な世界観を持った作品が多い、道原かつみ先生のマンガ。猫を祖先に持ち「人類に奉仕する」ことを遺伝子に刷り込まれたヒューマノイド達が住む、人類から捨てられた辺境の惑星を舞台にした話。自由に生きたいが刷り込まれた宿命から逃れられないヒロインの葛藤が印象的。女性読者向けSFコミックの奥深さを知った作品。
2007/08/02
■引っ越し後の本棚リストを公開したくなった(1995-2000年版)
お久しぶりです。前回の本棚自慢の続きです。今回は1995年~2000年のコミックを羅列。
なお、今週のサンデーはこれから読みます><
2000年
- 阿弖流為2世 (高橋 克彦/原 哲夫)
- 「
アメリカの次はエイリアンにNOだ!
」「捨て おけ!
」
原哲夫先生のマンガは、描かれた時代の雰囲気を反映していて面白いですよね(穏便な表現)。 - がんばれ酢めし疑獄!! (施川 ユウキ)
- 現在は「サナギさん」を描いてる施川ユウキ先生の出世作。不条理ギャグと言うよりも哲学ギャグと表現した方がいいかも知れない。作者のセンスが妙に私の性に合います。
- あずまんが大王 (あずま きよひこ)
- 「女子高生が日常を緩やかに消費する」系マンガの金字塔的な作品にしてデファクトスタンダード。中毒的なまでの再読性の高さは今以て魅力的。
- MISTERジパング (椎名 高志)
- 現代椎名高志マンガの礎。このマンガが完全に消化できなかった「予知によって決められた未来への抵抗」というテーマを「絶チル」が受け継いでいるのではないかと思ってます。
1999年
- 愛人 AI-REN (田中ユタカ)
- 田中ユタカ先生が、エロマンガ家としてのキャリアを賭け、己の持てる全ての才能を注ぎ込んで造り上げた魂の結晶。読むと心を揺さぶられること間違いなしな名作。こんなしんどいマンガを最後まで描き切ることができた田中ユタカ先生の気力は、本当に素晴らしいと思う。
- 公権力横領捜査官・中坊林太郎 (原 哲夫)
- 「
親は関係ないだろ、親は!おー!?
」があまりにも(ネタとして)有名なマンガ。原哲夫先生の画風とベタかつ破天荒なストーリーがマッチしており、何度読んでも楽しめる。『大衆向け娯楽マンガ』の魅力を体現したかのような作品。 - チャッピーとゆかいな下僕ども (ながいけん)
- リンクは大都社から出ている大増補版。みんな大好き(決めつけ)ながいけん先生の、最初にしておそらく最期の作品集。独自路線を行くギャグマンガ家としての希有な才能を存分に堪能できるが、あとがきを読んでいるとその「才能」があったからこそサンデーというメジャー誌ではやっていけなかったのかな、とも思う。
昔サンデー増刊に載った「極道さんといっしょ」を読みたいので、「モテモテ王国」の未収録分と含めてコミックスを出して下さい。 - スタンダードブルー (宇河 弘樹)
- 「朝霧の巫女」の宇河弘樹先生の初期作品。近未来の海洋都市を舞台に、父親を海で失った主人公の女の子が様々な経験を経て成長していく、という筋書き。個人的に海洋冒険モノが好きというのもあるけど、最終話の「父」の存在と向き合った上で大人へと成長していく流れが個人的にツボ。
- 進め!!聖学電脳研究部 (平野 耕太)
- 新声社版を所有。基本的には作者が好き勝手やってる変なマンガなんだけど、それ故に「アレな感じのゲームをネタにして楽しむ」オタク気質や、「情報に流されず本当に自分が好きなゲームを好きと言ってプレイする」コアなゲーマー気質といった、作者の世代のゲームファン達が持っていた雰囲気を伝えていることができている気がします。
- 半分少女 (流星 ひかる)
- 思春期特有の、甘酸っぱくてちょっとエッチでかつ少し不思議なマンガを描かせると圧倒的なアドバンテージを発揮する、流星ひかる先生のマンガ。先生のコミックは何冊か持っていたけど、悩んだ末に一番最初に買ったこれを残した次第。
- ホアー!!小池さん (藤子 不二雄A)
- コンセントレーション!(挨拶) 藤子不二雄A先生でなければ到底許されないキャラクターやストーリーが跋扈する、色々な意味でAテイストに溢れたゴルフマンガの怪作。これが本当のAだ!(決めつけ)
- 羊のうた (冬目景)
- 持っているのはソニーマガジンズ版。自分が冬目景という漫画家の魅力を知ったマンガ。主人公の姉の千砂の美しさと純粋な意味でのエロティシズムが忘れられない。あと八重樫さんの健気さも忘れられない。今も自分の心に深く余韻が響いている作品。
1998年
- 魔術っ子!海堂くん!! (すがわら くにゆき)
- ポップな絵柄のキャラ達が軽快かつ大胆なオタクトークを全編に渡って炸裂させる、すがわらくにゆき先生の作品。「
ひょーっ!やっぱりエロ同人はいいのう!
」「死んじゃえばいいのに
」「ちんこが二本も三本もっ!
」「貴様こそアニメとマンガと声優以外の話題で会話してみやがれっ!
」等、素敵な台詞が飛び交うマンガ。
初めて読んだ時はカルチャーショックを覚えました。ある意味、自分のオタク人生に大きな影響を与えたといって良い一冊。 - 大同人物語 (平野 耕太)
- 同人オタク達をスタイリッシュに描いた異色作。
こんなマンガを描けるのは、おそらく平野先生しかいません。 - 神聖モテモテ王国 (ながいけん)
- ひるいなき孤高のギャグマンガ。90年代のサンデーに「黄金期」があったとしたら、それは「モテモテ王国」が連載されていた時期だと思います。
1995-1997年
- 電波オデッセイ (永野 のりこ)
- 電波系なギャグの中に「社会になじめない者達の苦悩」というテーマを込めてマンガを描いてきた永野のりこ先生の作品の中でも、メッセージ性が極めて強いマンガ。
当時このマンガに救われた人も、きっと多いはず。 - グルームパーティー (川島 よしお)
- 「昭和時代の辛気くさいネタ」と「かわいい女の子」のミスマッチが絶妙な雰囲気を醸している四コママンガ。「女囚さそり」をインスパイアした「さそりちゃん」シリーズがもの凄く好き。故に永久保存。
- モジャ公 (藤子不二雄)
- 小学館コロコロ文庫版を所有。1969年に描かれたマンガ。
基本的には「21エモン」と同系統の宇宙冒険モノなのだが、このマンガから感じる死のオーラの強さはもはや尋常ではない。ブラックユーモアが冴え渡った藤子スペースオペラの傑作だと思う。こんなハードなマンガを低学年を対象とした雑誌に連載した藤子F先生はやはり偉大だ。
2007/07/29
■引っ越し後の本棚リストを公開したくなった
お久しぶりです。
サイトの更新が止まっていた間、主に何をやっていたかというと、引っ越しをしてました。
引っ越しの時点で、家にはこれまでの人生で買い込んできたマンガが大量にあったのですが、さすがにそれを全て持って行くのは物理的に無理なので、かなりの量の本を引っ越し時に処分しなければならなくなりました。具体的に言うと、マンガ用の本棚代わりにしていた三段のカラーボックスが10個あったんですが、新居に置けるのは2個だけという状況。約80%の本を処分しないといけません。
仕方がないので、捨てるか残すかの基準を以下のように定めることにしました。
- コミックス20巻を超える長期連載マンガは、物理的に保存が難しいので基本的に処分
- 読み返す頻度が低く、かつ入手難易度が低いもの(本屋や古本屋で容易に見つけられるもの)は処分
- 捨てるか残すか迷ったら「
このマンガの存在は、今の自分の人格を構成する要素になっているか?
」と問いかけ、「Yes」と応えられるものは保存。自信がなければ思い切って処分 - 椎名高志先生のコミックは、上記の第3項に基づいて保存
そんな選考を生き抜いて一緒に引っ越して来たマンガのうち、既に連載が終了している作品に絞ったリストを作ったので公開してみます。絞ったとはいえかなり量があるので、今回はコミックスが2001年以降に発行されたものを。
これってちょっと去年マンガ感想サイトで話題になったナツ100っぽいですね。参加したかったなあ(去年の夏の自分に向かって)。
2004年
- 武装錬金 (和月 伸宏)
- 読むと無闇に元気になって、人類の存在を賛美したくなるマンガ。それが「武装錬金」。自分がマンガという媒体に求めている楽しさが集約された作品なのかも知れない。
- 暁の歌 (藤田 和日郎)
- 藤田先生の短編集。伝説の名作「美食王の到着」のために購入したけど、一見弱々しい爺さんが実は柔術の達人だった!という筋書きの「瞬撃の虚空」のあまりの凄さにやられた。何度読んでもグッと来る。藤田先生は本気で底が知れないマンガ家だと改めて認識させられた一冊。
- 無敵鉄姫スピンちゃん (大 亜門)
- みんな大好き大亜門先生の出世作にして、大亜門作品のエッセンスがぎっしり詰まった傑作。でもやっぱり明らかな問題作であることは間違いない。その辺ひっくるめて好きな一冊。
2003年
- G-onらいだーす (小野 敏洋) [Amazon]
- 一見すると「
何故これが上連雀三平名義じゃないの?
」と思ってしまうくらいの完膚無きまでなパンツ履いてないマンガなのだが、しかしその本質は「博愛」の精神の尊さと美しさを描ききった名作である! と断言していきたい。 - セツナカナイカナ (こがわ みさき)
- すこし不思議系少女マンガ。表題作「セツナカナイカナ」と「マチコの心のへそ」が印象に残っており、時々読み返してホエホエしたくなる本。
- 玄米ブレード (雷句 誠)
- 雷句先生の新人時代の読み切りマンガ集。原初の雷句美少女のステキさを感じられる「ユリネグレイト」、原初の雷句ヒーローの心意気を感じさせる「ヒーローババーン」。原初の雷句誠の魅力が詰まった一冊。
- Cotton (紺野 キタ)
- OLやってる普通の大人の女性が、自分よりも背が高くて自己主張の激しい女子高生に振り回されつつも惹かれていくという感じの話。最終話でこの二人が泣きながらケンカするシーンがなんかもの凄く好きだ。なんだこの感情。
- 椎名百貨店超GSホームズ極楽大作戦!! (椎名 高志)
- 「カナタ」と「絶チル」の間を結ぶミッシングリンク的な作品を収録。「絶チル」好きな人でまだ未読なら是非。
ホントはこの勢いで「パンドラ」(兵部じゃない方)もコミックス化して欲しいところなんだけど、「絶チル」アニメ化級のイベントが起きないとダメなんでしょうか。
2002年
- ひみつの階段 (紺野 キタ)
- 乙女は祈る―ひみつのドミトリー (紺野 キタ)
- いわゆる女子校寄宿舎モノのエッセンスが詰まった傑作。持っているのは復刻されたポプラ社版の方。「マリみて」ブームのおかげでこういう作品が手に入れやすくなったのはありがたいです。
- エマ (森 薫)
- 連載は終わってませんが一応ここに。
現代メイドブームの礎を築いたと言っても過言ではない作品。自分の好きなモノを好きとアピールし続ける姿勢の大切さを森薫先生から教えてもらった気がします。 - おにいさまへ… (池田 理代子)
- 持っているのは中央文庫のコミック版。全編に渡って理不尽なまでの愛憎怨怒が吹き荒れる、女子校ソロリティモノの傑作。出崎統監督のアニメ版はこれに輪をかけた大傑作なので、第一話だけでもいいからみんな見るべき。
なお自分の脳内設定では、「マリみて」の水野蓉子は中学生の頃に「おにいさまへ…」のアニメ版を鑑賞、その中で描かれたソロリティのリーダー・一の宮蕗子の末路を目の当たりにして『ああはなるまい…
』と心に誓い、リリアンではソロリティの改革開放路線を掲げるようになったことになっています。 - ブラック・ラグーン (広江 礼威)
- 連載はまだ終わってませんが、ロックが己の立ち位置を決める覚悟をした6巻を読んだところで自分の中では一区切り付いたので、続きの購入が止まっている状態です。そろそろ続き買いたい。
- 地球美紗樹 (岩原 裕二)
- 岩原裕二先生のコミックは「いばらの王」も「クーデルカ」も持っていたのですが、眼鏡っ子とショタっ子がいちゃいちゃする「地球美紗樹」が個人的には一番ツボに来ました。
- ネコの王 (小野 敏洋)
- 「
異なる思想や人種が同じ世界に共存するためには?
」という現代的なテーマを提示しつつも、エンターテイメントに徹して楽しく読むことができる、小野敏洋先生のテイストが感じられる良作。 - 一番湯のカナタ (椎名 高志)
- 欠点は多いが愛するべきところも多い、あらゆる意味で微妙な立ち位置にいる椎名マンガ。3巻のハチャメチャさはある意味ファンなら必読。
2001年
- EVE★少女のたまご★ (やぶうち 優)
- 「
人間に愛されるロボット
」となるべく、少女型ロボットのイヴが小学校に通いつつ成長していく話。子供向け少女マンガとして普通に面白いし、成長過程の表現の仕方に巧みさを感じる。あと何かエロい(最大の保存理由)。さすがやぶうち優先生。 - なつのロケット (あさり よしとお)
- 小学生達が集まって「本物」の宇宙ロケットを作るという、あさりよしとお先生らしいジュヴナイルにしてハードSFなマンガ。文句なしに傑作。男の子はみんなこれを読んで熱くなるが良いと思う。
- ゆめのかよいじ (大野 安之)
- 所有しているのは新バージョンの角川書店版の方。ノスタルジーを基調としつつも、『時と共に変化する世界を是とも非ともせず、ただ緩やかに変化を許容する』、みたいな雰囲気の作品と認識。少女同士のエロスを想起させる雰囲気も良い。
- こさめちゃん―小田扉作品集 (小田 扉)
- 「小田扉」の名を知らしめたであろうコミックス。個人的には、コミティアで氏の同人誌を読んで衝撃を受けた「放送塔」が忘れられない。後は「としごろとしこ」のとぼけた感じも大好き。そんなお年頃なんですよ。
- 紺野さんと遊ぼう (安田 弘之)
- フェティシズムマンガの傑作(多分)。このマンガに漂う、嘆美を通り越してシュールとしか表現しようのない異様な雰囲気が大好き。オレはこういうのが好きなのかと自覚させられた本。
- プラネテス (幸村 誠)
- 近未来宇宙SF不朽の名作。人は宇宙への情熱を失ってはいけないと思う。しかし、「
タナベは俺の嫁
」でググると1件しか出てこないのはどうしたことか(と言われても)。
2007/02/15
■2006マリみて感想サマリー
この前、新書「ミッション・スクール」に関してちょっと書きましたが、そういえばここで「マリア様がみてる」についてここ1年くらい何も書いていないなとふと思ったので、これまで溜まっていた分の単行本の感想みたいなものを書いてみます。
なお、相変わらず自分の中では「マリみて」と「シグルイ」は不可分なので、ちょっとシグルイも混じってます。ご了承下さい。
くもりガラスの向こう側
ISBN:4086007436
『ただ一つの誤算は この夜の小笠原清子が正気でも曖昧でもなく
』
敵であろうと味方であろうと 間合いに入ったもの全てを斬る魔神へと変貌をとげたこと
そんな感じで、普段は曖昧な清子小母さまが魔神と化し、小笠原家の屋敷で大はしゃぎして大暴れするエピソード。いやマジで。
『マリア様がみてる』の宣伝文句は「超お嬢さま達の大騒ぎ学園コメディー」なので基本的にはこういう話もアリなのですが、祐巳が瞳子にこっぴどくフラれて失意のどん底にあるこのタイミングで「大騒ぎコメディー」的な話を祐巳に強要するとは容赦がないなあと思いました。お嬢さまやるのも大変だ。
仮面のアクトレス
ISBN:4086007843
『危ない
』
不十分な「ツンデレ」はそれゆえに危ない
かつて『未来の白地図
』で、その研ぎ澄まされたツンデレの刃で見事一撃で祐巳を斬り捨てた瞳子。ツンの技の冴えはもはや留まるところを知らず、神妙の域にまで達しつつある彼女ではあったが、しかし本来ツンデレとは「ツン」と「デレ」が不可分の存在であり、一度ツンの刃を祐巳に向けたからには、いつかはその刃を収めてデレに移行しなければならない。
だが瞳子はあまりにツンが過ぎるあまり、祐巳に対して刃を収めるタイミングを逸してしまっていた! 今、鞘を見失った瞳子のツンデレの暴走が始まる!
みたいな感じで、行き所を失いつつあった瞳子が感情の収まりどころを探して生徒会選挙に立候補した話だと理解しているのですが、その辺どうでしょうか。
大きな扉 小さな鍵
『四名目として生徒会選挙に立候補したのは 紅薔薇さまの親戚である松平瞳子であり
』
その瞳子を制したのは やはり紅薔薇さまの妹である福沢祐巳
恐るべしは 同門と言えども命を賭して薔薇さまの座を競う紅薔薇流
市井の風評はそのような形に落ち着いた しかし
キーホルダー編:
読者の視点からは瞳子にフられてからどうにも煮え切らないでフラフラしているように見える祐巳ですが、でも彼女の周囲の人達はそんな祐巳の態度を余裕と貫禄の表れと解釈し、「あれだけされても瞳子を見捨てないで見守っているなんて、さすがは祐巳さま!
」と、その大物っぷりに感心する話だと解釈しました。
「彼女には何か自分には判らない事情があるようだから、しばらく時間を置こう」という祐巳の消極的とも言える選択が周囲の共感と協力を呼ぶこととなり、結果的に事態を好転させることになります。これも祐巳の人徳のなせる技か。さすがは将来リリアンを支配する運命にある女は違う!
ハートの鍵穴編:
今となっては瞳子の「お兄さま、おしっこ!
」しか記憶に残っていない方も多いと思いますが、全てに対して疑心暗鬼になっている瞳子が、「お兄さま」こと柏木との会話を通じて自分が如何に周囲が見えていない状況に陥っているかを自覚した、という意味においてかなり重要なエピソードであると言えます。
「お兄さま、おしっこ!」は、同じく自分のことで疑心暗鬼に陥って自分勝手に怒りに震え始めたお兄さまを制すると共に、自分もお兄さまと同様の状態にあることを彼女が自覚したことを暗示する言葉でもあるのです。
でも「おしっこ」はやりすぎだと思った。お兄さまおしっこ。ハァハァ(ダメ)。
クリスクロス
ISBN:4086008599
『リリアン女生徒による学園狩りが二度行われたが
』
成果はカード二通
ツンデレの刃を誤って振るっていたことを自覚し、行き詰まってしまった瞳子。彼女が内心で「救い」を求めている正にその時、これまで祐巳や瞳子の動きをあえて静観していた祥子さまが、ついに動いた! という話。瞳子が自らの意志でバレンタインイベントに参加し、祐巳に会って状況を打開できるように背中を押す(しかも祥子さまらしくひねくれた方法で)そのやり方は狡猾そのものであり、さすがは陰謀渦巻く女の園で支配者として君臨しているだけのことはあるよなあと思いました(まちがい)。
そして、祥子とは逆に一貫して瞳子に介入して来た乃梨子も、前巻で彼女が感じた祐巳さまの大物っぷりを瞳子に説くことで、ついに瞳子を動かすことに成功。さすがは祐巳さま亡き後に「マリみて」の主役を張る女と噂されるだけのことはありますね(ありますか?)。
ヒントは出しても決してカードを探し出せない場所に隠した志摩子さんは、本当に性格が悪いと思いました。
□
そんな感じで、去年の「マリみて」は総じて『瞳子が祐巳の妹になるかどうか』というネタで散々引っ張ってきたイメージが強く、「祐巳と瞳子が姉妹になってイチャイチャしてるところを読みてえ!」と常日頃から妄想しているファンの方は切ない時を過ごされたのではないかと思われますが、「クリスクロス」で瞳子が動き出したことでようやく話が先に進みそうな雰囲気になって来ました。
今年こそは、祐巳と瞳子がイチャイチャしてるところを本編でも読めるようになれるといいですねー
| ISBN:4253230466:awssmall: | ISBN:4253230474:awssmall: | ISBN:4253230482:awssmall: |
2007/02/04
■ミッション・スクール
「マリみて」の蔦子さんの名前は、『蔦の絡まるチャペルで祈りを捧げた日』で始まる「学生時代」から来ていたという説を展開!(挨拶)
マンガではないですが、せっかく読んだのでちょっと紹介。
「マリア様がみてる」の大ヒット以降、この界隈でも物語の舞台としてよく使われるようになったミッションスクール。この本は、近代日本におけるミッションスクールなる存在に対する社会的なイメージの時代による移り変わりを、様々な文献や文学作品を紐解いて解説しています。
この本が我々にとって面白いポイントは、現代におけるミッションスクールに対する大衆イメージの代表例として、「マリア様がみてる」の巻頭に載っている『「ごきげんよう」「ごきげんよう」
』から始まるあの文章を紹介しているところ。この本の著者の佐藤八寿子氏は、序章において「マリみて」の巻頭文を引用した上、リリアン女学園は作者が創作した架空の存在であって実際にはこのような学園は存在していないにも関わらず、『非常にリアルにわれわれのイメージするところのミッション・スクールを描き出している
』と述べます。
いかにもそれ「らしい」断片から構成されたのが、作者オリジナルのリリアン女学園なのだが、われわれはそこに違和感を覚えない。むしろ、どこにも実在しないリリアン女学園は、私たちの「中」にあるミッション・スクールを如実に体現している。では、私たちの中にあるミッション・スクールとはどのような存在なのか。
(ミッション・スクール 6ページ目より)
この疑問を出発点として、「マリみて」で語られているようなステレオタイプな「私たちの中にあるミッション・スクール」のイメージが如何に形成されていったのかを、明治から平成までの時代を追う形で解説しています。
紹介されている文献は、明治時代の新聞記事から田中康夫氏のエッセイに至るまで多岐に渡りますが、特に大正~昭和にかけての文学作品や映画に見られる「ミッション・ガール」(ミッションスクールに通う女学生)についてはかなり詳しく考察と分析が行われており、結果的に「ミッション系女学生で観る近代文学史」として読むことができるようになっているのが面白いところ。
また、戦後における「ミッチーブーム」も取り上げており、美智子さんが幼稚園から大学まで一貫してミッション系の学校に通っていたことがミッションスクールのブランドイメージを大きく向上させた、としています。「マリみて」に出てくる「十八年間通い続ければ温室育ちの純粋培養お嬢さまが箱入りで出荷される
」ってのは、この時に形成されたミッションスクールのイメージを反映させたものなのかな、とか思いました。
こんな感じで、「マリみて」に代表されるステレオタイプなミッションスクールの大衆イメージは、明治以降の長い歴史を経て形成されていったものである――ということがよく判る本です。
基本的にはミッション・スクールに本気で興味がある人が読む本ですが、「マリみて」とかのミッションスクールが舞台の少女小説が大好きな人が読んでも楽しめるのではないかと思いました。
また、最後の方には自分の娘をミッションスクールに入れたくて仕方がない父親の話も出てくるので、娘ができたらリリアン女学園に! とか、今度生まれ変わったらリリアン女学園に入って、紅薔薇さまの信奉者に! とか本気で妄想している人にもお勧めしておきます。
2006/03/01
■マリア様がみてる・未来の白地図感想
マリア様がみてる・未来の白地図 後半のあらすじ
断ゆることなき未来への不安が
触れるもの全てを疑い! 憎み! 引き裂く!
瞳子にふさわしい姉など居ないのだ!
「気に入った!
この祐巳と共にリリアンを駆ける妹は、それくらい気性の激しい方が良い!
何としても おまえをいただく!」
(つづく)
ちなみに元ネタは、「覚悟のススメ」10巻の散と霞の着装シーンです。
3月にマリみての新刊が発売されるとの情報を掴んだので、今更ながらマリア様がみてるの(現在の)新刊「未来の白地図」の感想を簡単に書きます。
この巻で印象に残ったのは、やはり瞳子のツンツンっぷりです。彼女は現在、我々読者には与り知らない理由で窮地に立っているようなのですが、そんな彼女の心境を察してついに自ら手を差し伸べた祐巳に対しても「聖夜の施しをなさりたいなら、余所でなさってください
」と冷たい言葉を返して一撃で葬り去る、道理を超えた大理不尽なまでのツンっぷりがお見事。むしろお美事。
瞳子が内心では祐巳の存在を求めて止まない状態であることは既に「特別でないただの一日」以降の彼女の動向を見れば明らかな上、何らかの理由で彼女は自身の将来に対して何らかの不安を感じており、今まさに誰かの助けを必要としている状態であることは自分でもよく判っているであろうにも関わらず、それでも差し伸べられた手を「哀れみからの施し
」と解釈して拒否せざるを得ない彼女の心理たるや、もはや尋常なものではありません。
「賭けとか同情とか、そんなものはなしよ。これは神聖な儀式なんだから
」
祥子が祐巳を妹にした時の言葉こそ今の瞳子には必要なはずであり、また祐巳も祥子がこの言葉を発するに至った境地に達することが必要なのだと思うのですが、まだ当の祐巳は自分が瞳子を「妹」にしようと思った心理が何であるかを明確に自覚できていない以上(祐巳が瞳子を妹にしようとした理由を「何となく
」と表現していることが、それを象徴しているような気がします)、今の状態ではさすがの祐巳も、極限までひねくれて爆発寸前な瞳子に差し伸べた手を受け取ってもらうのは無理なのも仕方ありません。
不完全な状態でうかつに手を出したりしたら、瞳子に再びしかるべき因果を極められてしまうのは必至であります。
おそらく次巻以降で、何故瞳子が現在の心理状態になるに至ったのか? という説明描写が入ることで二人の状況は変化すると思われますし、何より一度瞳子に因果を極められた祐巳が懲りずに「何としても おまえをいただく!
」みたいなことを言っている以上、最終的にはこの二人は姉妹の形で落ち着くのではないかと予想はできるのですが、でも実際にこの二人が姉妹となって「鋼我一体! 心はひとつ!
」とか叫びながら血盟を果たすまでには、まだまだ相当の艱難辛苦が予想されます。
OVAで発売されるアニメ版が全てリリースされるのが先か! それとも、小説版の中で祐巳と瞳子が姉妹になるのが先か!
「マリア様がみてるプロジェクト2006」は、まだ始まったばかりなのだ!(←年末までこのネタを引っ張りかねない予感)
2005/06/23
■マリみて感想・妹オーディション
マリア様がみてる・妹オーディション前半のあらすじ:
『黄薔薇のつぼみ』の中目録を持つ島津由乃は、秋になってもまだ妹を見つけられないでいた。
「山百合会の看板に泥を塗られ申した!」
「一刻も早く妹を見つけねば! まごまごしていると江利子さまが嘲笑いはじめ申す!」
「物笑いになってからでは遅い! 一度潰れた面目は二度とは戻りませぬゆえ!」
「一応の妹を立てる」
私の頭の中では何故か「シグルイ」と「マリみて」が不可分の関係になっているため(理由)、シグルイ4巻を購入した直後、不覚にもまだこのサイトで「妹オーディション」の感想を書いてないことを思い出しました。なので今更ながら書きます。
もうすぐ次の新刊「薔薇のミルフィーユ」が発売されるので、次刊への期待も込めて。
(一応注意:以下は「妹オーディション」のネタバレをバリバリ含みます)
□
「妹オーディション」の表面的な主人公は島津由乃なのですが、真の主人公はやはり福沢祐巳。
そんな巻でした(感想)。
福沢祐巳というキャラは、物語の焦点が「祐巳の妹は誰になるのか」という点に移った時期(「涼風さつさつ」以降)から、「仲間のことになると気が利くけど、自分のことになるとまるっきり鈍感」というキャラクター性を持つようになります。
この巻は、彼女のそんなキャラクター性が、余すところなく発揮されていました。
まず前者の「仲間のことになると気が利く」ポジティブな側面に関しては、茶話会に参加して来た内藤笙子に対して「彼女が求めているものは、山百合会ではなく武嶋蔦子だ」ということを直感的に見抜き、この二人を掛け合わせるために様々な策を講じて暗躍した、物語後半の活躍が強く印象に残ります。
また、ミスをした下級生にミスを指摘しつつ的確なリカバリー方法を指示したり、結局落選した妹候補達にフォローを入れ、彼女たちの今後の山百合会に対するわだかまりを軽減する努力をするなど、下級生に対して細やかな気配りができるようになったことを読者にさりげなくアピールしている点も、小さい部分ではありますが見逃せません。
これらは、彼女が『紅薔薇さま』として生徒達をまとめる能力を既に有しつつあることを、端的に示していると考えられます。
由乃の妹となるべき運命を授けられた少女・有馬菜々が中学三年生であったことから推測できるように、「マリア様がみてる」という物語は彼女たちが「薔薇さま」と呼ばれる立場になった以降も継続することがほぼ確実な情勢なのですが、そういう意味でも「福沢祐巳は下級生に人気がある」という(これまでは単に文章で説明されている程度だった)設定を補強し、彼女がいずれ最強の薔薇さまと呼ばれるだけの才覚を持つことを印象付け、将来の更なる成長を読者に期待させる意味合いもあったのかも知れません。
かつて水野蓉子が夢見た「一般生徒で賑わう薔薇の館
」を実現できるのはおそらく祐巳だけですし、彼女ならおそらくそれを成し遂げてしまうでしょう。「マリア様がみてる」には山百合会というソロリティを舞台にした学園物語という側面を持ち合わせていますが、その物語に『ゴール』があるとすれば、そのうちの一つは間違いなくこれになるのではないかと思われます。
その一方、「自分のことになるとまるっきり鈍感」というネガティブな側面については、祐巳にすっかり恋い焦がれるようになってしまった松平瞳子の苦悩という形で、より明確に現れて来ています。
祐巳が「自分の妹候補」を探すために茶話会を開いたという事実は、瞳子の目には「祐巳は自分を妹候補として特別視していない」サインとして映ったはずです。彼女はこのサインに対し、茶話会への参加をかたくなに拒否するという形で応えました。
見かねた乃梨子が遠回しな表現で「茶話会を開くことが瞳子にとって何を意味しているのか」を祐巳に伝えたのですが、鈍感な祐巳には全く届かず、逆に瞳子の無念を想った乃梨子が涙を流す羽目に。
祐巳は、これまで瞳子に対して『優しく』接して来た結果、彼女が自分に対してどんな感情を持つようになったのか、まったく気付いていません。というか、今の彼女ではそのことを想像すらできないでしょう。誰にも分け隔てなく優しさを振りまけられるところが祐巳の長所ではあるのですが、それ故に祐巳との「二人だけの特別の関係」、すなわち姉妹関係を望む者にとっては、その優しさが自分だけに向けられたものではないことを妬ましく感じるはずです。
自分にとってその人は特別で、その人も自分を特別な人として見て欲しいのに、その人から見れば自分は特別でも何でもない。その人の優しさはその人自身の中から来ているものに過ぎず、決して優しさを向ける相手が自分だからではない。それが判っているが故に、優しくされるのが辛い。それが今の瞳子の状態なんだと思います。
あの瞳子をここまで悩ませるだなんて、祐巳ちゃんもすっかり罪作りな女になっちゃいましたよねえ。
□
まもなく刊行される「薔薇のミルフィーユ」は、本の構成が各薔薇ファミリーを主人公にした短編が一話づつ、合わせて三話の構成になることが既に告知されていますが、これはあの「レイニーブルー」と構成が全く一緒であり、ファンの間からは「次の巻は、瞳子にとっての『レイニーブルー』みたいな位置付けの話になるのではないか
」と噂されているとかいないとか(どっちだよ)。
「妹オーディション」でストーリーが大きく進展した後だけに、どんな話になるのか楽しみです。
とりあえず今の段階で確実に言えることは、今度の夏のコミケで「脱ぎかけ制服な格好で『撮って撮って』と蔦子に迫る笙子の姿を描いた同人誌
」が必ず出てくることですね。見つけたら買います。勿論、乃梨子×瞳子本も見つけたら買います。
集英社 (2005/04/01)
2005/04/23
■今更マリみて新刊感想
「マリア様がみてる」における『姉妹の契り』は時折『婚姻』にも例えられますが、『涼風さつさつ』において祐巳が可南子相手に「いい子だとは思うんだけど、いざ妹にするとなるとちょっとなあー
」とか色々妄想していた姿に、周囲から縁談を薦められて「悪い人じゃなさそうだけど、でもこの人とお付き合いをするとなるとちょっとねえー
」と悩む自分の姿を重ね合わせてしまった経験がある、適齢期逸脱間際の善男善女の皆様こんにちはー!(挨拶)
その件についてはノーコメント。深沢です。
今更ではありますが、以下はみんな大好き超お嬢様わんさかコメディー「マリア様がみてる」最新刊・「特別でないただの一日」の感想です。いやその、急に書きたい気分になったのでつい。「マリみて」は時々熱がぶり返すのでヤバいです。
もう発売から1ヶ月以上経過しているので、ネタバレ前提でお願いします。
□
この巻が発売された当時、「マリみて」読者の最大の興味は、何と言っても「主人公の祐巳が誰を『妹』に選ぶのか?」ということであったのは間違いないでしょう。折しもこの巻が扱っている『学園祭』という舞台設定は「マリみて」第一巻で祐巳が祥子と姉妹の契りを結んだきっかけとなる事件が起こったという史実があるので、当然この巻では「祐巳が妹を誰にするかを決める、決定的な事件か何かが起こるのでは?」と期待する読者が多かったのではないかと思われます。
…でも、その結果は皆さんも読んでご存じの通り。この巻の存在意義は、一番最後のシーンで祥子さまが祐巳に「妹を作りなさい
」と言う状況を作るための壮大なネタ振りに過ぎなかったのではないか、と申しても過言ではないお話でした。
「学園祭の一日は、祐巳にとって特別なものになるのではないか」という読者の期待感を、「特別でないただの一日」というサブタイトル、そして一番最後のシーンで祥子が祐巳に語った「今日は特別でも何でもない、昨日と変わらないただの一日よ
」という台詞で完全にひっくり返してしまった作者のセンスと(良い意味での)底意地の悪さには、心底惚れ惚れさせられます。
さすがはダブル受賞作家! センスが違いますね!(←私が言うと褒めてるように聞こえなくなるのは何故ですか)
とは言うものの、話の中では最初から最後まで祐巳の「妹」候補である松平瞳子と細川可南子の動向がクローズアップされており、読者のそういう興味を更に掻き立てる効果を果たしたのもまた事実。
瞳子が所属している演劇部で派手に問題を起こしたり、前々から張られていた可南子の「極度の男嫌い」(というか人間不信)の伏線の回収劇が多くの人を巻き込みながら壮大なスケールで繰り広げられたりと、どちらも負けず劣らずの暴れっぷりを披露してくれました。
主人公の祐巳はどちらの騒動にも深く関与する(そして、結果的にそれが二人が抱えているそれぞれの問題の解決に繋がる)ことになるのですが、騒動の渦中にいる瞳子と可南子が祐巳と接する時の態度が、何だかラブコメみたいで微笑ましく思えて来るのが面白いところ。わざわざ祐巳と二人きりの時に学園祭の演劇の不満を愚痴り始める可南子といい、祐巳の視線を感じた途端にわざとらしく顔を背ける瞳子といい、どちらも過剰なまでに祐巳の存在を意識しているのは明らかです。
二人とも口では「祐巳さまの妹にはなりたくない」と言ってはいるものの、実際にはどちらも祐巳にかまって欲しくて仕方がないのが歴然な描写がなされているので、彼女たちが祐巳と絡むシーンが出てくるたびに、私はもう始終ニヤニヤしっぱなしでした(悪趣味)。
そして、今回の物語をより(色々な意味で)面白くしているのが、主人公の祐巳の天然ボケっぷりです。彼女は祥子お姉さまや友人のことになると勘が冴えるのですが、こと自分自身に関してはてんてニブいままであり、自分がどれだけ周囲からモテモテな状態になっているのか、この段階になってもまだ彼女は自覚していません。
祐巳はこの巻においても、可南子や瞳子の「妹にはならない」発言を真に受けたまま、罪のない天使のような好意を彼女たちに向け続けています。可南子や瞳子は、上で述べたように彼女の存在を強く意識してはいるものの、自分から「妹にはならない」と言った面子もあるし、それに祐巳が自分の世話を焼こうとする感情にはまったく他意がないこともよく判っているため、祐巳の好意を知らないフリしてやり過ごすしかありません(物語後半の瞳子がまさにこの状態)。祐巳が接するたびに、彼女たちの緊張感は高まっていく一方なのです。
そんな緊張状態の真っ直中に居ることを知らず、無邪気に振る舞い続ける祐巳の天然っぷりには、もはや微笑ましいを通り越して何だか怖ろしくなって来てしまいます。彼女のこの態度は、そう遠くないうちに何かとんでもない事態を引き起こすんじゃないか、と思えてなりません。
今の祐巳をこのサイトらしく例えるなら、「MISTERジパング」に出てきた蜂須賀小六のこの台詞が適当かも知れません:
「火薬庫で火遊びする奴は二種類しかいねぇ。
」
何も分かってないバカか、よっぽど火の扱いに自信のあるバカだ!!
「ミスジパ」の信長はどちらかと言えば後者に当てはまるタイプでしたが、祐巳ちゃんは自分が火薬庫にいることも、また自分が火遊びをしていることにも気付いていないという意味で、信長をはるかに超越していると思いました。
さすがは、近い将来リリアン女学園を支配する女王となるであろう運命の持ち主! 器の大きさが違いますね!(←私が言うと褒めてるように聞こえなくなるのは何故ですか)
この巻では「特別でないただの一日」という表題通り、姉妹関係については表面上の変化はありませんでしたが、でも可南子や瞳子と祐巳との関係は更に深まり、また緊張も高まりました。もはや、ちょっと祐巳が二人に対する態度を間違えたり、どちらかが本気で「妹にして下さい」とか言い出したりしたら、今の人間関係は一気に崩れてしまいかねません。この巻の最後の祥子さまの台詞「妹を作りなさい
」は、そのことにあまりにも無自覚な妹に対して認識を改めさせる狙いがあったのではないか、とも思えてきます。
そんな感じで、次回以降一気にヒートアップするであろう「祐巳の妹選び」のストーリーを楽しみに待ちたいと思いました。
□
あと、こちらも諸般の事情で嫁選びを迫られている由乃の方ですが、こっちは祐巳と違ってどのキャラに対しても全くフラグが立たず、祐巳と漫才やっただけで終わってしまいました。祐巳はモテすぎちゃってヤバいんですけど、由乃は逆にモテなさ過ぎてヤバいことになっています。
これはおそらく、このまま(劇中で)11月になっても妹が見つからず、困った挙げ句にそこら辺の知り合いの1年生を捕まえて「これから来るOGの前でしばらくアタシの妹のフリをしてくれない?」と頼み込み、山百合会の面々を巻き込んで周囲に散々迷惑をまき散らした挙げ句に江利子に一発で見抜かれてギャフン! みたいな、吉本新喜劇的なコテコテの展開をするための伏線と見ましたがどうか。
そういや彼女の姉の令さまもすっかり「ヘタレ」のキャッチフレーズが似合う芸風になってしまいましたし、黄薔薇一族はどんどんヨゴレ役化して行く一方です。微笑ましい限りですね。
□
※一応補足しておきますが、本来「マリみて」は姉妹制度をキーワードに少女同士の心の交流と成長の様を描いた少女小説であり、今回の「特別でないただの一日」でも可南子と瞳子がそれぞれ事件を通じて「相互理解」の必要性を自覚する様子が描写されています。一応、その辺はちゃんと判ってるつもりですので!(言い訳)
おそらく次回以降では、今回とは逆に祐巳がこの二人を理解しようとする様子が描かれるのではないのでしょうか。
なお、マリみてを「相互理解」というキーワードで判りやすく論じているサイトとしては、「ランゲージダイアリー」(あいばゆうじさん制作)がお勧めです。「mot×mot」の時代から楽しく読んでました(カミングアウト)。
「ガンダムSEED DESTINY」や「武装錬金」の感想も熱いので、そちらが好きな方もぜひ。
■いきなり最近読んだ本紹介:役割語の謎
「そうじゃ、わしが博士じゃ」としゃべる博士や、「ごめん遊ばせ、よろしくってよ」としゃべるお嬢様に、実際に会ったことがあるだろうか。現実に存在する・しないに関わらず、いかにもそれらしく感じてしまう言葉遣い、それを役割語と名付けよう。誰がいつ作ったのか、なぜみんなが知っているのか。そもそも一体何のために、こんな言葉があるのだろう。
(ヴァーチャル日本語 役割語の謎より)
この解説文に思わずグッと来てしまい、「ヴァーチャル日本語 役割語の謎」(金水敏/岩波書店)を購入。
期待に違わず、知的興奮を感じさせてくれる興味深い一冊でした。
□
この本は、「博士言葉」や「お嬢様言葉」に代表される、その言葉を喋るだけでその人物がどのようなカテゴリーに属しているかを表現することが可能な「役割語」が何時どのようにして発生したのか、また我々が(実際にそんな喋り方をする人はほとんど実在しないにも関わらず)それらの言葉を聞いただけで「この人物は博士だ!」「お嬢様だ!」とステレオタイプを認識できるのは何故なのか、を探ることを目的としています。
役割語の元になった言語の起源から、その言葉が「役割語」に変わっていく過程までを、数多くの資料を引用しながら判りやすく解説するスタイルで書かれています。個人的に興味がある分野だったこともあって、最初から最後まで楽しく読むことができました。
また、このような喋り方をする人物が登場するのは主に小説やマンガといった大衆向けの娯楽文学であることが多いので、結果的にこの本は近代~現代にかけての文学史やコミック史を辿るような形になっているのが、我々のような本好きな人にとっては興味深いところ。
実際、この本の中では「怪談牡丹灯籠」「東海道中膝栗毛」「吾輩は猫である」「ハリーポッター」「鉄腕アトム」「名探偵コナン」「エースをねらえ!」、果ては「ファイナルファンタジーIX」に出てきた語尾に「クポ?
」とかつけて喋る変なキャラに至るまで、「役割語の謎を探る」という括りの中で一緒くたになって参考資料として扱われています。何というかこう、たいへんに愉快です。
例えば『博士語』を解説している第一章では、今サンデーで連載されている「名探偵コナン」の阿笠博士が喋っている言葉の源泉を辿っていくと、「鉄腕アトム」のお茶の水博士→昭和初期のSF作家・海野十三の作品に登場する博士たち→明治時代の講談師が語った時代劇に登場する忍術の師匠、といった具合にどんどん時代を遡っていき、最終的には江戸時代中期に書かれた戯曲や歌舞伎に登場する老人が喋っていた上方言葉にたどり着くそうです。
「名探偵コナン」が江戸時代にまで繋がっているだなんて、ちょっと興奮してきませんか博士。子供相手に変なガジェットを発明して喜んでる場合じゃないですよ博士。
あと、役割語の最大の特徴は「この言葉を喋らせれば、キャラとして細かい描写をしなくても『こいつはこんなキャラだ』と認識してくれること」であるので、趣味でマンガや小説書いてる人にとっても、この本に書かれている役割語の使われ方は参考になるかも知れません。役割語の歴史は近代文学の歴史でもあるのです。
ただ、フィクションの世界の役割語はあくまで「『役割語』から連想される程度の人物描写があれば十分な脇役キャラ」に対して使うのが本筋であって、逆に『主人公』は標準語を喋らないと読者が感情移入し辛い、とも解説しています。役割語には、視聴者や読者が感情移入するべき主人公とその他大勢を切り分ける仕掛けとしての役割もあり、実際数多くの物語がそれに基づいて作られていることを、この本は説明しています。
とりあえずここは椎名高志ファンサイトなので、宇宙人であることを強調するために主人公の台詞の語尾に「カナ?
」という役割語をつけたからと言っても、それだけでキャラクターが面白くなる訳ではなかったのであった! というオチで良いでしょうか。
なつかしいなあ「一番湯のカナタ」(おわり)。
2005/04/20
■ブックレビュー:お嬢さまことば速修講座
「覚悟」とは苦痛を回避しようとする生物の本能すらも凌駕する魂の事であるが、
「お嬢さま」とは己の気品と尊厳を以て世界と戦う意志を秘めた、気高き魂の有り様の事である!
そんな感じで、週末に出かけた先の本屋にあった「お嬢さまことば速修講座」(ディスカヴァー・トゥエンティワン、監修:加藤ゑみ子)を買ってしまいました。本の存在は知っていて前からちょっと気にはなってはいたのですが、書店で本物を見た途端に私の中の乙女要素が疼いてしまってつい。
ごきげんよう(挨拶)。
それでこの本、タイトルに「速修講座」と銘打ってあるだけあって、いわゆる「お嬢さまことば」を使って会話をするためのコツが、要点を押さえた形で簡潔にまとめられているのが特徴です。文体が「ベテランの礼儀作法の先生がお嬢さまに心得を説く
」ような形になっているので、読んでいるうちに自然と自分が「お嬢さま修行中」みたいなマインドセットになること請け合い。
内容も、実際に「お嬢さまことば」を使う人の喋り方をリサーチして作成されたと言うだけあって、極めて実用的で判りやすく作られています。
曰く、
- お嬢さまなので、「どうも」の代わりに「
恐れ入ります
」を使う。
「どうも」と言ってしまうとお里が知れる。 - お嬢さまなので、語尾に「こと」「の」「て」を付ける、いわゆる「
ことのて結び
」を使って雰囲気を醸し出す。「ですね」→「ですこと
」、「そうですか」→「そうですの
」、「いいの?」→「よろしくって?
」等々。
これらをマスターしないうちにお嬢さまを気取ろうとしても、お里が知れるだけである。 - お嬢さまなので、何か質問されたら必ず「
さようでございますか
」と相槌を打つ。否定的な回答をする場合も、返答の言葉は同様。肯定・否定を曖昧に表現するのがお嬢さまである。
相槌に「ええ」「はい」を使う時は、決して二回以上重ねて「ええ、ええ」とは言ってはならない。使うとお里が知れる。 - お嬢さまなので、困った事態になったら沈黙を守る。あなたが本当のお嬢さまであるならば、慌てずにっこり微笑んでいるだけで、周囲の人々があなたのために事態を収拾してくれるはずである。
慌てて取り繕うようではお里が知れる。 - お嬢さまことばを使う時は、恥ずかしがらずに最後まで、ゆっくりした口調ながらも明瞭に喋ること。「
ごきげんよう
」の挨拶も元気よく。
語尾を省略したりすると、普段使い慣れない言葉を使っているのがバレてお里が知れる。
万事がこんな調子で、お嬢さまを演じきるために必要な心得や技術が一通り書かれてます。
この本を読む必要があるのはお嬢さまでも何でもない普通の人々ばかりなので、お里が知れて俗物扱いされてしまっては元も子もないのであります。
でもまあもっとも、実践編の最後の方にはちゃんと「どうせ相手も『お嬢さま』ではない可能性が高いので、とにかく照れずに自信を持ってお嬢さまことばを使え
」みたいなことが書かれているんですけどね。現実社会にはもはやリアルなお嬢さまはほとんど存在していないということは、本を作る側もちゃんと認識しているのです。
以前ここで紹介した「ヴァーチャル日本語 役割語の謎」にも書かれていたことですが、現代社会における「お嬢さまことば」とは、『この言葉を使う人はステレオタイプなお嬢さまである』ことを表現するために存在している、限りなくフィクションに近いものに過ぎないのです。実際にお嬢さま言葉を使っているのを耳にしたことがあるのは、アニメ版「マリア様がみてる」の小笠原祥子さまの台詞だけ! なんて方も多いのではないのでしょうか。
では、何故今あえて「お嬢さまことば」を使うのか。この本では、それを「気品」という言葉で説明しています。
お嬢さまことばを使う効能として、この言語体系で喋ろうとすると、自然と語り口が謙虚で慎み深く丁寧な、いわゆる「お嬢さま」っぽいものになることが挙げられます。お嬢さまことばを操るためには知性が必要なので、喋りながらも「短縮せず、ゆっくり、最後まで」を心がけながら常に頭を働かせることで、自然と慎み深く丁寧な、気品を帯びた口調になるのです。
即ち、お嬢さまことばには独特の「気品」が宿っており、それ故に使う者の言動や考え方を律する効能があると考えられます。言葉が自分に馴染んで行くに連れ、「お嬢さまことばを使う自分」を自己肯定的に捉えるようになり、やがてその人は自然とその言葉を発するに相応しい気品と人格を宿すことになるでしょう。
そして会話の相手に対しても、「丁寧に喋るお嬢さまと会話をすることで、自分の社会的な立場を高められた感覚」を与えることができ、その相手もまた自分をそれ相応の人物として尊重して接するようになる――と、この本は説きます。相手と自分が相互に高め合う関係になることができれば、自分の「お嬢さま」としての立場は相手が作ってくれるのです。これこそが、お嬢さまことばの本当の力であると言えます。言葉には魂が宿ると申しますが、お嬢さまことばには文字通り「世界を変える力」があるのです。
「マリみて」にも、祥子さまにお嬢さま口調で話しかけられた書店員が、彼女の気品っぷりに圧されて突然丁寧な口調になって返答するなんてシーンがありましたけど、これは現代でもお嬢さまことばの力が十分通用することを端的に象徴したエピソードであると言えましょう。
現代社会でお嬢さまことばを使うということは、相当にしんどいことです。ヘマすれば簡単にお里が知られてしまい、高貴なお嬢さまから「は、はわわわ~
」なドジッ娘に地位が逆戻りしてしまいかねませんし、更にはせっかく習得したお嬢さまことばを他人の悪口を言うことに費やす、お嬢さまの暗黒面に目覚めてしまう可能性があるのもまた事実。
しかし、お嬢さまことばが世界を変える力を持つ言葉である以上、使う者にもそれ相応の心構えが必要になるのです。例えば、「マリみて」の小笠原祥子さまはほとんどの局面においてお嬢さまことばを使いますが、これは単に「彼女は生粋のお嬢さまである」という作品内の記号的な意味合い以上に、「彼女はお嬢さまことばを常に使うことで、己の気品を保とうとしているのだ」と知ることが重要なのです。彼女は親しい人相手にもあえてお嬢さまことばを使うことで、彼女の世界を彼女自身が「お嬢さま」として気高く振る舞うに相応しい場所にするため、あえて日々世界と戦って学園の品位を上げようとしているのです。
祥子さまはただの根性曲がりじゃないんですよ! クィーンオブ根性曲がりなんですよ!(うるさいよ)
なお、「お嬢さまことばで罵声を浴びせられたい!
」と懇願したいどうしようもないマゾヒストな貴方には、この本の巻末にちゃんと「お嬢さまらしいけなしことばリスト」が掲載されているので、「ふくよかでいらっしゃる!
」(デブに対する言い回し)「お派手な趣味でいらして!
」(悪趣味な人に対する言い回し)などの、なまじ政治的に正しいためにかえって怖い言葉の数々を祥子さまヴォイスで脳内再生し、存分に悦に浸って頂きたい。
またbk1にトラックバックできないような書評を書いてしまいました(書評?)。
2004/08/03
■「マリみて」短編・図書館の本
先週は職場の夏休みだったということもあり、少女マンガや少女小説などの乙女チックな物件を中心に買いあさって悦に浸ってました。夏なので(関係ない)。
そんな訳で、せっかく色々買ったので簡単なレビューを。不定期に追加していきます(理由:買ったはいいけど読んでないものばっかりなので)。
□
隔月刊コバルト8月号(集英社)
この号に掲載されている「マリア様がみてる」の短編『図書館の本』の評判が、ファンの間でやたら良さそうだったので(生まれて初めて)購入。
『図書館の本』の読後、何故か頭の中に「覚悟のススメ」の瞬殺無音部隊長・葉隠四郎が現れて
「何よりも強きもの! 母と子の絆!
」
さらに強きもの! 帝国(リリアン)と軍人(生徒)の絆!
と邪悪な笑みを浮かべながら呟く、コミックス10巻の光景が浮かんでしまいました。どうしよう。
やっぱり、「マリみて」と山口貴由のマンガって相性がいいのかな!(オレの頭の中でだけ)
そんな感じで、「リリアン女学園」はあらゆるものを結ぶ"絆"としてあまねく世界に遍在している――というこの作品独特の世界法則に沿った、短いながらもキレイにまとまっているお話だと思います。ファンからの評価が高いのも納得。
読んでいて感じたのが、「小説」という表現媒体の利点を活かした物語の進め方(というか、肝心の「謎」の伏せ方)の巧妙さ加減。同じ雑誌の中には正直「これって、小説じゃなくてマンガで表現するべきお話じゃ?」と思ってしまうものもあっただけに、作者の今野氏の「小説」ならではの表現手法に感心させられました。やっぱり、伊達に人気作家やってないね!(エラそう)
あと今号のコバルトには、前田珠子先生の作品も載ってました。その昔「破妖の剣」シリーズが好きだった私としては、氏がまだ現役で書いてるのが確認できてちょっと嬉しかったり。『破妖の剣』を最初に読んだのは、確か今からもう15年くらい前のことでした。
ところで、結局「破妖の剣」って、まだ完結していないのでしょうか。ここだけの話ですが、自分が死ぬまでにやっておくべきToDoリストの中には、「もし『破妖の剣』が完結したら、まとめて買って読むこと
」という項目があるので、ちょっと気になってます。
まあ、「マリみて」も今のペースではあと15年経っても絶対に完結しないと思うので、どちらも完結する時を気長に待つことにして行きたい。退職金でコバルト文庫をまとめ買いする、そんな第二の人生を夢見る今日この頃です。乙女ちっくな夢だ(ウソ)。