2007/08/25
■シグルイ9巻
『人か魔か牛股権左右衛門
』
獣かそれ以下か 鬼かそれ以上か
ここで「シグルイ」の感想書くのも久しぶりなような気がします。
で、前巻のシグルイ8巻は、「剣術」という戦闘技術の究極に行き着いた藤木源之助・伊良子清玄両名の技の応酬を理論整然と描いた、非常に繊細な話だったという印象だったのですが、この9巻では源之助の片腕が落ちたと同時にそんな繊細さはもはや微塵もなくなり、魔神モードに入った牛股権左右衛門が内蔵をまき散らしながら大暴れする姿を読んで呆気にとられるしかない、という話に早変わり。
8巻の頃から牛股がずっと我慢してきた「ここにいる全ての輩を片端から斬り殺してしまいたいという衝動
」が、ここに来て大爆発してしまったのでしょうか。
また自分の記憶だと、原作における牛股が虎眼流を継げない理由は「既に結婚して奥さんがいるから」だったと認識していたのですが、この「シグルイ」だとなんか許嫁を殺害した上に自分の睾丸を(以下略)、みたいな話になっていてちょっとビックリしました。でもこれは「シグルイ」であり、「シグルイ」である以上はこれくらいのことは当たり前なのです。
この巻を読んで、シグルイ4巻で虎眼先生が鯉を生でボリボリ囓っているのを目撃した牛股師範が「ごゆるりと…
」と呟いて静かに退散した時の心境が理解できた気がしました。今の山口貴之先生は、緩慢な時の虎眼先生くらいに絶好調だと思います。よく判らない表現ですが誉めてます。
2006/12/06
■会長はメイド様1巻
久しぶりにサンデー以外のマンガの感想ー!
マンガ好きな人なら既にご存じの「会長はメイド様!」を、ようやく読むことができました。以下短観。
読んでちょっと驚いたのが、冒頭にメイド喫茶に関する説明的なシーンやカットが全く入っていないところ。主人公がメイド喫茶でアルバイトをしていることが読者に提示される最初のシーンが、(お約束的な「おかえりなさいませご主人さま~」的なシーンではなく)主人公がメイドの格好で「こんなバイトやめときゃよかった
」とやさぐれた台詞を言いながら巨大なゴミを出しているところであるのが、何か凄いなと思いました。何というかこう、エルフやドワーフとは何かという説明が全くないまま、これらの亜人種がいきなり出てくるファンタジー小説を読んだ時みたいな感じ。そうか、お嬢さんはドワーフを知ってる人なんだね。みたいな(なにそれ)。
現代日本において、既にメイド喫茶はコスチュームを出すだけで「あー」という感じで読者がその全てを納得できる程までに一般的な存在になっているんだなあ、と改めて思った次第です。
もっともこのカットは、主人公の性格、彼女の「メイド喫茶」なる存在に対するスタンスの表明、そしてこのシーンの直後にライバルの男子にバレるというバツの悪さをひっくるめて全てが必要不可欠なものであり、ある意味このマンガの有り様を象徴していると思われます。
普通のマンガであれば「おかえりなさいませご主人さま~」を持ってくる状況であえてこんな演出を持ってくるところに、作者のセンスを感じました。
そんなアレで「主人公のカタブツ生徒会長が、みんなに内緒でメイド喫茶でバイトしている」という設定そのものは奇抜なんですけど、基本的なストーリーは「弱みを知られたライバルの美男子に反発しつつも、次第に彼のことが気になって(以下略)!
」的な、少女マンガとしては極めてスタンダードな構成になっており、安心して読むことができる作品だと思います。
何より、常に毅然として凛とした意志の強さを持つけど決して我が強いだけの少女でもない、主人公の美咲がとても魅力的。男子に生まれたからには、こんな生徒会長に一度でいいから隷属したい! と思わせるに十分です。
気が強い女子が大活躍する系のマンガが大好きな(かつ、この手の少女マンガに抵抗がない)人にはお勧め。
2006/08/20
■夏休みの友
飲み会の当日、山田さんから「こわしや我聞」の藤木先生が作った同人誌「夏休みの友」を頂きました。ありがとうございます!>山田さん
それでこの本の中身ですが、要するに我聞のメンバーがそろいも揃って「絶チル」4巻のおまけコミックみたいな騒動をする話です。つまり温泉ネタ。
ご本人が「サービス精神10割増し」と仰っているように、陽菜さんや果歩や桃子のありがたい裸がたくさん拝める、ファンとしてはとても嬉しい内容になっているのが特徴です。特に、桃子の裸のエロさはただ事ではありません。
でも裸のコマ数からすると、一番脱いでるのは我聞ではないかという気がしますが。我聞のポロリがないのがちょっと残念(残念?)。
何にしろ、藤木先生が楽しんで作ったことが誌面からもよく判る、作者の愛情溢れるとても楽しい本だと思いました。
勿論、この調子でサンデーでの早期の新連載も超期待したいところ。こういうマンガは、やっぱり本誌で堂々とやって頂きたいです! 藤木キャラのポロリが読めるのはサンデーだけ! みたいな感じで一つ!
2006/04/02
■メモ:少年マンガ誌の現在
毎日新聞社発行の「まんたんブロード」に掲載された、更級修一郎氏インタビューによるマガジン・サンデー・チャンピオン各誌の編集長インタビュー記事が、現在ネットで公開されています(更級修一郎氏のブログのエントリより)。
今も梶原一騎的ダイナミズムを志向するマガジン、今もあだち&高橋作品の強い影響下にあるサンデー。
共通するのは、80年代までに形成されたスタンスを踏襲し続けていること。
そして識者の座談会では、子供向けの娯楽に徹するスタイルを90年代後半から洗練させたジャンプは強い、という話題に。
出席者達がみんなジャンプの話題になると何となく饒舌になるのは、やっぱそれだけ今のジャンプには識者を語らせたくなるモノがあるからなのかなあと思った。
2006/03/15
■第4回仁川経済大学コミックアワード
もうネットでは旧知の話題になってしまいましたが、みんな大好きバーチャルネット博士こと駒木さんのサイト「駒木博士の社会学講座」で開催された「第4回仁川経済大学コミックアワード」において、ついに連載版「絶対可憐チルドレン」がグランプリの栄冠に輝きました。
駒木博士のところのコミックアワードは、ネット上におけるマンガ評論の権威として確立しているイメージがあるので、そこで「絶チル」が最高の形で評価されるというのはファンとして純粋に嬉しいです。
これでコミックス5巻の販促の帯には、「これぞエンターテインメント!! 2005年最高傑作と評された『絶対可憐チルドレン』」とか書かれること間違いなしですネ!
「絶チル」はグランプリと同時に『ジャンプ&サンデー最優秀長編作品賞』も受賞しているのですが、その受賞理由として書かれている
「『絶対可憐チルドレン』はとんでもない作品です。どれくらいとんでもないかと言うと、何もかもが巧過ぎるので、普通に読み飛ばしてたら全く凄い事に気付かないぐらい、とんでもない(苦笑)。
」
というコメントが、「絶チル」が如何に完成度が高いマンガであるのかということを、とても判りやすく表現していると思いました。
つまり「絶チル」の何処が凄いのかというと、マンガとして基本的なことを極めて高いレベルで自然に実現しているところが凄いのだ! ということなんですよね! ハカセ!(←誰?)
□
そしてそれと同時に、「現代マンガ時評」を含む定期更新の終了もアナウンスされました。
ここ最近は明らかに更新するのが辛そうな雰囲気だったので、この決定も致し方ないと思います。
駒木博士のサイトは既に「権威」としての地位を確立していると思うのですが、それ故に「自分の立場を考えて、発言内容にもっと配慮して下さい
」と受講者から言われてしまう程の大きなプレッシャーを駒木さんに与えていた訳であり、その期待に応えるだけの評論活動を行うモチベーションを(趣味の範疇で)これまで保ち続けて来たのは、とても大変なことだったことは想像に難くありません。
今まで本当にご苦労様でした。しばらくの間、ゆっくり休養して下さい。
あと、ぶっちゃけチャット大会の日程が決まりましたらぜひ参加したいと思いますので連絡下さい(笑)。
2006/03/14
■MISTERジパングを読んでいだ時の違和感を思い出した
お久しぶりです(挨拶)。仕事で頭がテンパッていたので更新停止してました。
「ピアノ・ファイア」のいずみのさんが、「椎名高志のコマ割りグセ」というエントリにおいて椎名高志マンガにおけるコマ割り(と、それに伴う問題点)について書かれていたので、それに対して色々考えたことを(あまりまとまってませんが)書いてみます。
特にコマ割りに関しては、椎名高志は極楽大作戦の時代から「1ページのコマを6コマ以上に割らない」というスタイルを通している(大体3~5コマが普通で、6コマに割るのは珍しい)と思うのですが、そのコマ密度の低さに対して、1話あたりのストーリー展開が早いという要素が災いして、しょっちゅう説明不足な場面を生んでます。
ギャグにしろ見せ場にしろ、「オチを出すのが早い」「起承転結の承や転(タメ)が足りない」印象を度々受けました。場面と場面がうまく繋がらなくて、一瞬ワープしているような気にさせる。
んで、この「オチを出すのが早い」「タメが足りない」という現象は、今連載中の『絶対可憐チルドレン』でも良くあるんですよね。おそらく、MISTERジパングの頃についてしまったクセが作者に残ってるんだと思います。話のオチをいきなり出したり、キャラクターの感情が高まりきる前に大ゴマをバーンと出して決め台詞を叫ばせてしまったり。「作者が見せたい結果」だけを脈絡無しに描いているような。
ピアノ・ファイア 「椎名高志のコマ割りグセ」より引用
「MISTERジパング」の頃は、コマ割りについてはあまり気にならなかった(というか、マンガを読んでいてコマ割りを気にすることはなかった)のでそれに関しては何とも言えないのですが、当時リアルタイムで連載を読んでいて「リズムが悪い」と感じることが何度かあったことは記憶しています。キャラクターが自発的に喋っているのではなく、ストーリーに沿うように台詞を喋らされているように読めてしまうが故のノリの悪さというか、そういうタイプの違和感を当時持っていたのは確かです。
それが、いずみのさんが『「作者が見せたい結果」だけを脈絡無しに描いている
』と指摘しているところではないか、と思いました。
ミスジパの時は、椎名氏が自ら「日吉が思うように動かせなかった」みたいなことを完成原稿速報に書いたり(参考:Wayback Machineによるログ)していた時期もあったので、当時は色々と悩んでいた面もあったのではないかと推測しています。
そして現在の「絶対可憐チルドレン」ですが、これまで以上に意図的に大コマを使っていると感じることはよくありますね。基本的には「能力バトル」系のマンガなので、絵的なインパクトを最重要視した演出をしている印象を持っています。
また「絶チル」では、「MISTERジパング」の頃のようなリズムの悪さを感じることは(個人的には)かなり減って来ています。特にコミックス3巻以降に収録されたエピソードでは、読んでいてその手の引っかかりを感じたことはほとんどありません。この頃から個々のキャラクターのパーソナリティが(作者にも読者にも)明確になり、作品そのものにも勢いが出て全体的なノリが良くなったというのもありますが、連載に人気が出て来たおかげで一つのエピソードに話数を費やすことができる余裕が生まれるようになったから、という理由もあるのかなと思っています。
ただ、それでも「本来作者が構想していたストーリーから実際に誌面に落ちるまでの間で、相当プロットを削ぎ落としているんだろうなあ」と感じることは多々あります。前回の「ナショナル・チルドレン」編でも、グリシャム大佐の話芸をギャグとして大コマで見せることを最優先にし、その一方で本来ならストーリーのメインに据えるであろうはずの「過去の彼とおかっぱ少女との思い出のノスタルジー描写」は大胆に削って、『読者が考えて補完してもらう』方向にあえて持って行ってるフシがあります。
こういう省略の仕方ができるのはマンガというメディアの特性であり、椎名氏はそういった記法が許されるマンガの文法を読者が把握し、意図を読み取る能力を持っていることを期待してマンガを作っているのではないか、と思います。ここまで表現すれば後はついて来てくれるだろうという、(良く言えば)読者の知性を信頼したマンガの作り方です。これは、特に近年の椎名マンガで顕著になって来ている傾向だと分析しています。
これは、言い方を変えれば「マンガだから許される表現に頼っている」とも言えますが。「ナショナル・チルドレン」編を原作のテイストを活かしたままアニメ化するのは、結構大変そうだなあと思いました(気が早い)。
あとコマ割りで思い出したのですが、「ラブひな」を読んでいた頃はよく「何故この人(赤松健先生)は、こんなに細かくコマ割りをしてまで1話でストーリーを進めようとしているのだろう。このボリュームだったら2話くらいに分割できそうなのに、もったいないなあ
」とか不遜なことを思っていたのですが、これは自分の頭が椎名高志作品的なコマ割りのリズム(3~5コマ)に慣れているため、赤松健作品のコマ割り(6~8コマが基本?)を「細かい」と認識していたからだったんだろうなと、いずみのさんのエントリを読んで思い至りました。
コマ割りの仕方でマンガの表現方法を観察してみるのも面白いですね。
マンガを読む際の新たな視点を与えてくれて、ありがとうございます。
2006/01/31
■「ネギま!で遊ぶ…エーミッタム!!」を読みました
「エーミッタム」を「エミッターイム」と間違えて記憶!(挨拶)
今更な話題になりますが、執筆陣の豪華さと赤松健先生ロングインタビューが掲載されたことで話題となった「ネギま!で遊ぶ…エーミッタム!!」を、ようやく読むことができました。
この本を読んで個人的に一番印象に残った言葉は、いずみのさんによる赤松健先生へのインタビュー記事における、『ファンが「赤松健論」で行っているようなテーマや作品構造を深読みすることに対して、どう考えているのか?』との質問に対する
「深読みしすぎですよね(笑)
」
という、赤松氏の冗談めかしたような回答でした。
氏はインタビューの中で、「私はソロバンづくでなんでもやってるようにみんな思っているのかもしれませんけど、実際には(原稿を)上げるだけで精一杯
」とわざわざ手の内を明かし、その上で「『実は赤松は裏でこう思ってるんじゃないか』って思ってくれる分には凄く助かるんですよ
」と、作者の思惑以上に深読みをして来る読者に対する謝意を、素直に表しています。
この「ネギま!で遊ぶ」という同人誌は、編者のTaichiroさんが仰っているように「作品をより主体的に楽しむ」面白さをライトなファンに伝えることを目的として作られたものと思われますが、作者の赤松氏自身がこの本に代表されるようなファンの評論活動に対して極めてオープンなスタンスを取っていることは、ファンにとって極めて幸福なことではないかなと思います。
この辺は、パソコン通信の時代から自分のファンと積極的にネットを通じて交流して来た、赤松氏ならではの感覚なのでしょう。
自作への読者の思い入れを「邪魔」や「迷惑」と思わず、逆に読者がそういう行為を行うことに対して感謝の意を表する、作者のゆるやかでオープンな姿勢が、「ネギま」がここまでファンの間で熱心に語られてるようになった理由の一つとして上げられるのではないか――そんなことを感じたインタビュー記事でした。ファンがファン活動をすることで幸せになれるマンガ、それが「ネギま」。そんな感じ。
例え作者自身は毎週毎週原稿を上げるだけで手一杯で、読者が思っている程深いところまで考えてはいないとしても、自分が作った作品世界をファンが各々の解釈で『解読』して行く様子を、赤松氏は楽しんでおられるのかも知れませんね。
この懐の広さ! この貫禄っぷり! さすが大物は違う!
あと寄稿された記事の中では、Fuku Diaryの(福)さんによる「ショタ漫画として読むネギま!」に激しく共感致しました。
そうそう、そうなんですよ。「ネギま」の中で一番可愛いキャラは、絶対ネギ君で決まりなんですよ。「ネギま」が少年の成長物語として成立しているのは、今のネギ君の少年らしい可愛らしさが作品の根幹にあるが故なんですよ! みんな判れ!
特にネギ君の尻の可愛らしさったら、もう! 今度生まれ変わったら千鶴姉さんになって、ネギ君の尻にネギを(←おちつけ)
■ネギま12巻
せっかくの機会なので、ついでに今更ながら「魔法先生ネギま!」コミックスの感想も。
まず12巻ですが、この巻で個人的に印象に残ったキャラは、やはり千雨。口では何だかんだ言っていても、自分の力が及ぶことならついついネギに協力してしまう、彼女の「いい人」っぷりの描写が良かったです。
世間でツンデレ呼ばわりされるのも納得。
あと職業柄、千雨がどうやって匿名掲示板を中心に盛り上がっていたネット上での魔法疑惑の打ち消し工作を行ったのかに興味があるのですが、私の予想では彼女は匿名掲示板のまとめサイトを自ら設営、そこで全体としては魔法の存在に否定的な見解をもつように編集を行った上で自分のサイト上でこのまとめサイトを紹介し、「ネットアイドル」としての立場を駆使してネット上にまとめサイトの存在を伝播させてネット世論を操作する――という、まとめサイトが持つ情報の伝播力+ネットのオーソリティとしての自己の立場をフル活用する戦法でネットの波に立ち向かったのではないか? と勝手に推測しています。
何にしろ、この巻の彼女は、この作品世界には魔法やアーティファクトを用いるだけではなく、ネットを知り尽くしているが故に可能な戦い方もある、ということを示していたと思いました。「噂を操る能力」こそ、彼女の持つ本当の魔法の力。かっこいいなあ千雨。
もしオレがソーシャルネットワークサービスを手がける会社の社長だったら、長谷川千雨を真っ先にスカウトするところです(変な例え)。
また、12巻の冒頭で明日菜の小さい頃の話が出てきましたが、これはアニメ版の設定をインポートして来たという解釈で良いのでしょうか。
アニメ版は、個人的には第一話の冒頭1分で挫折してからちゃんと観ていなかったこともあり、なんか「もし『ネギま』が文化祭編に入る前に打ち切りを食らったらどうなっていたか?」という歴史上のifを追求したような話だったという印象なんですけど(ダメ)、ちゃんとマンガ本編の方でサポートするなんて義理堅いなあと思いました。
2005/08/09
■最近読んだコミックスの突発感想
成恵の世界8巻
ISBN:4047137367:awssimple:SFとラブコメとパンツに満ちあふれた、みんな大好き「成恵の世界」の最新刊。
SFマインドはこの巻でも相変わらず健在。この巻の表題作「時台屋の女房」で周囲の世界が徐々に過去に退行していくシーンがジャック・フィニィの「ゲイルズバーグの春を愛す」を彷彿とさせ、個人的にちょっとグッと来た。あと「SHOOTING STAR」は物言わぬ機械と人間が心を通わせる話、というだけで超グッと来る。何を考えているのか判らない機械は常に萌え対象だ。
またラブコメ的な部分も、「時台屋の女房」の超時空レベルの恋愛劇の他、香奈花の微妙な乙女心の変化を描いた「お熱いのはお好き?」、中学生レベルのほのぼのしたエロティシズムに溢れた「トラぱら」と、どれも心に来る良作。
そして勿論「成恵」と言えばパンツだが、この巻では特にバチスカーフのパンツと野球部マネージャーのパンツが印象的だ。SFとラブコメとパンツが高いレベルで融合した面白さがここに。
ここ最近の「成恵」の中でも、かなり完成度が高い巻なのではないかと思った。中学生以上のオタク男子なら必読レベルのクオリティを絶賛キープ中。
サナギさん1巻
ISBN:4253210112:awssimple:
四コママンガが衰退傾向にある週刊少年誌界において、「グルームパーティー」「O-HA-YO」「がんばれ酢めし疑獄!」と四コママンガの良作をリリースし続けている週刊少年チャンピオンで現在連載中の四コママンガがコレ。
作者は「酢めし疑獄」の施川ユウキ氏。
表紙や帯はサザエさん系の「ほのぼの四コママンガ」を連想させるように作ってあるが、実際の中身は作者独特の黒みがかったユニークなユーモアセンスに満ちあふれているのが特徴。主人公のサナギさんの笑い声の擬音で一番多いのがよりによって「ゲラゲラ
」であるところが、このマンガのギャグの傾向を端的に表していると思われる。
サナギさんと友達のマフユちゃんの間のどこか歪んだ会話を中心に、常にネガティブな妄想を抱いているサダハル君と彼に強烈な突っ込みを入れる短気なタカシ君、常に物事に対してケチを付けなければ気が済まないリサさん、事ある毎に何かを踏まなければ気が済まないマナミさんといったおかしなキャラクターが、何とも言えない変な味わいを醸し出すマンガが満載。何度読んでも飽きが来ない、優れた「世界」を持つ作品と言える。
ネタ的に何でもありだった「酢めし疑獄」から、「中学一年生の日常会話」に焦点を絞った「サナギさん」に連載が移行したことで、作者のユーモアセンスがより一層際だって来たような印象を受ける。
最近では朝日新聞で紹介されたことで一気にブレイクしたらしく、現在ではかなりの品薄状態になっている模様。まだ入手できる環境に居る方は、今のうちにぜひ。施川氏の出世作「がんばれ酢めし疑獄!!」も面白いのでぜひ。
ヨコハマ買い出し紀行13巻
ISBN:4063211711:awssimple:この巻を読んでいると、なんかこう無性にバイクで走り出したくなって困るよ!(感想?)
あと、この巻は「時間の流れ」を印象付けるようなイメージが強かった印象。一番最後に掲載されている「月の輪」に出てくる『もうふたまわりもでかくなったら また一人が好きになんかもしんねえし
』というおじさんの台詞には、アルファがこれまで経験してきた時間と、彼女が更にこれから経験するであろう長い長い時間を連想させる、深いものを感じさせる。
この巻に掲載されているそれまでの話が、登場人物が時間を経て変化したり成長したりする様子を(地味ながら)描いている話が多かったので、「月の輪」は尚更アルファというキャラクターが置かれている立場のせつなさを象徴するエピソードであったと思う。
このマンガも、長い間に色々と変化しているんだなと感じた。
2005/08/04
■月刊少年シリウスとテレパシー少女蘭
ゲツカンシリウス!(挨拶)
カタカナで書くと西尾維新の小説のタイトルっぽく見えるテスト終了。こんにちは。
講談社から5月に創刊された「月刊少年シリウス」。「コミックと小説の新世代ハイブリッドマガジン
」を標榜、ラノベ大好きな少年少女を狙い撃った雑誌という触れ込みの割には、現段階ではどうも「読めば面白いがひたすら地味」という評価を頂いてしまうレベルの知名度に甘んじてしまっている模様です。
そんなシリウスに現在連載されている、『テレパシー少女「蘭」 ~ねらわれた街~
』(原作:あさの あつこ/漫画:いーだ俊嗣)というマンガが個人的に相当ツボに入ってしまい、居ても立ってもいられなくなってしまったのでご紹介します。
□
このマンガは、『主人公の中学一年生・蘭(らん)のクラスに翠(みどり)という名の美少女が転校して来たのだが、実は彼女はテレパシーやサイコキネシスを操る超能力者であり、蘭に対して「あんたも私と同じ能力を持っている」と告げる』――という導入から始まり、蘭と翠が超能力で街で起こっている不思議な出来事に立ち向かっていくという筋書きの、SF仕立てのミステリーです。
「テレパシー少女」「転校生」「謎の美少女」「ねらわれた街」といったテクニカルタームから推測できるように、いわゆるジュヴナイル小説のテイストがかなり強いです。これを初めて読んだ時は、何だか子供の頃に読んだ「なぞの転校生」や「ねらわれた学園」と雰囲気がどことなく似ているなあ、と思ったんですけど、このマンガの原作となっている小説「ねらわれた街」を調べてみたところ、児童向け文庫の講談社青い鳥文庫に収録されていると知って納得。
「青い鳥文庫」の方では童画家の塚越文雄氏によるイラストが如何にも「児童向け」な雰囲気を醸し出しているのですが、月刊少年シリウスは基本的に西尾維新や田中芳樹の小説が大好きな中高生以上の年齢がターゲットとあって、キャラクターデザインはかなりソレっぽいものにチューンナップされています。詳しくはシリウス公式サイトの作品紹介ページを参照。このイラストだけでやられる人も多いんじゃないんでしょうか。マンガ版の作者のいーだ俊嗣氏のセンスの良さを感じます。
そして何より素晴らしいのが、「なぞの転校生」として登場した翠のツンデレっぷりです。ツンデレ。
彼女は、自分が超能力を持っていることで両親から疎まれるようになって現在は家族と別居しており、それ故に自分と同じ能力を持つ人間を探し求めていた――というバックグラウンドがあり、彼女にとって蘭はようやく見つけた「仲間」だった訳なのですが、でもそういう生い立ちに起因する弱みを見せまいとする意地っ張りな性格が災いしてか、最初のうちは蘭に対して素直な態度が取れません。
本当は仲良くなりたいのに、プライドが邪魔して悪口を言ってしまう。ツンデレで言うところのツン状態です。
しかしそんな彼女も、翠の心情を察した蘭の「ひとりじゃないよ…翠
」という言葉で陥落。人と違う能力を持って生まれ、常にさみしさや絶望に苛まれてきた翠は、その時初めて自分を自分として真正面から受け止めてくれる人に出会えたことを知り、蘭に心を許すようになります。
更に二人の周りで次々と奇妙な事件が起こり、この街が謎の「敵」に狙われていると知った二人は、超能力を駆使して共に戦う盟友状態の関係にまで一気に進展。ツンデレで言うところのデレ状態への移行です。
つまりこの作品は、タイトルこそ「テレパシー少女蘭」となっていますが、「テレパシーツンデレ少女翠」として読んでも十分に楽しめるものになっているのです。ツンデレエスパーですよツンデレエスパー。しかもツンデレ対象は同い年の少女。百合っぽいです。同じエスパー少女マンガの「絶対可憐チルドレン」にすらない要素が満載ですよ!(うるさいよ)
他にも翠は、普段はツンと澄まして綺麗な標準語を話すんだけど興奮すると急に関西弁になって一気に感情を爆発させたり、強力なサイコキネシス能力を持っていながらそれをクラスメートの首筋をサイコキネシスでつねっていじめるという極めて陰湿な使い方をしたりと、歪んだ性格の女性キャラが大好きな自分にとっては、もうやることなすこと全部ツボです。辛抱たまりません。
斯様に萌え萌えなキャラクターが児童文学の世界に存在していただなんてちょっと凄いよ! と思いましたが、でも本当に凄いのは、自社の児童文学の中から少年マンガの原作として立派に通用する作品を見つけ出し、その作品を適切な画風を持った漫画家に託して「少年マンガ」としてのフレーバーを与えることで作品の潜在的な魅力を引き出すことに成功した、雑誌編集者のセンスの良さにあるのではないのでしょうか。
ちょっと大げさな表現になりますが、「テレパシー少女『蘭』」は、「コミックと小説の新世代ハイブリッドマガジン」というこの雑誌の路線を象徴している作品なのではないか、と思いました。
シリウスには、他にも「ぼくと未来屋の夏」(原作:はやみねかおる/漫画:武本糸会)、「夏の魔術」(原作:田中芳樹/漫画:ふくやまけいこ)の小説原作シリーズがありますが、どの作品もかなり良質かつ面白いマンガになっています。漫画界には原作を書ける作家が不足している、だなんてことが言われているそうですが、原作のノベルと漫画を結びつける手法を雑誌の大きな「売り」として掲げた月刊少年シリウスの作戦は、現状の原作不足に対する一つのソリューションとして興味深い事例になるかも知れません。
――というか、ここまで萌えるツンデレがいるのにネット上であまり話題にならないこと自体が、月刊少年シリウスが地味な雑誌の地位に甘んじていることの証明になっている気がしてならないのですが。「テレパシー少女 シリウス」でググっても54件しかヒットしないだなんて何事ですか! こんなに萌えるのに! こんなに萌えるのに!(連呼) もっとがんばって売り込め講談社!
今本屋で売ってるシリウス9月号には、翠が蘭に対して「ツン」から「デレ」に状態遷移する決定的なイベントが収録されているので、そういうのが大好きな方はチェックを! せめてこのマンガがコミックス化されるくらいまでは雑誌が存続してくれないと困りますからね!(ドクロ)
あと、来月号からは「暗号名はBF」の田中保左奈先生の新連載「乱飛乱外」も始まるので、とりあえずここのサイトを覗いているようなタイプの人はチェックしてみる価値はある雑誌なんじゃないか、と思いました。終了。
ライトノベル発祥以前の、往年の児童向けSF小説の雰囲気が好きだった方なら楽しく読めると思います
2005/05/10
■GW中に読んだマンガの感想特集(いきなり)
さよなら絶望先生
「久米田康治」というネームバリューから期待される社会風刺ネタの冴えは相変わらずだが、その辺を抜きにしても、マンガとして普通に面白い作りになっているのは流石だと思った。「進路絶望」がそのまま「進路希望」として他の教員に通用してしまう第2話のオチには激しく感動。パロディの元ネタ探しも楽しいけれど、読者の「知性」を刺激してニヤリとさせる話をさらりと作って読ませるところこそが、久米田先生の真骨頂なのではないか。
問題は、こういうセンスがどこまで「一歩」で「クニミツ」で「ネギま」なマガジン読者に判ってもらえるかどうかという点か。案外、半年くらいであっけなく終わっちゃう可能性もあるような気がする。
あと、天敵の赤松先生が、久米田氏がマガジンっぽくない個性丸出しな作品をぶつけて来た件に対して「こういう戦法が通じたのはCLAMP先生だけ
」みたいなコメントでその先行きを危惧していたが(4/26の日記)、でも個人的にはCLAMP先生もマガジンでは相当ダメージ食らっているのではないかと思う。ただ、CLAMP先生はゴッグ並に頑丈なので、「さすがゴッグだ何ともないぜ」理論でダメージを食らっていない様に見えているだけなのではないか。どうでもいいか。
失踪日記
吾妻ひでお氏が失踪中に経験した社会の底辺における様々な出来事を、自らライトかつドライに綴った問題作。早くも今年度のマンガ賞を総ナメするのは必至と思われる傑作(というか怪作)。
内容だけど、野宿生活編がやっぱり凄い。人間ってこんな極限状態に置かれても生きられるものなのか、と思うと同時に、案外こんな生活でも「生き続ける」だけなら何とかなるものなのか、とも思った。でも多分後者の感想は、吾妻先生の絵柄に騙されてるに違いない。あとアル中はやっぱダメなので気を付けよう。
個人的には「先生ほどの方が何故!
」と驚いている、ロリコン警官に激しく共感した。そりゃこんなところで憧れの大先生に会ったらビックリするよなあ。「夢」と色紙に書かせたりするのも仕方ないよなあ。
のだめカンタービレ
前々から「面白い」と聞いていたマンガではあったんだけど、「講談社漫画賞受賞!
」のアオリ文句に根負けして購入(弱い)。とりあえず3巻まで読んだけど、評判以上に面白い。音大という場所じゃないと存在が許されなさそうな奇人変人ばかり出てくるところがステキ。さすが「平成よっぱらい研究所」を描いた二ノ宮知子先生は違う。何かが。
基本的には社会不適合者以外の何者でもないヒロイン役ののだめがやたら可愛く思えてしまうのは、主人公との掛け合いの面白さによるものなのか。それとも、やっぱり「これくらいの歳の娘はこれくらいおかしい方がカワイイんだよね!」と思ってしまいがちな、自分の歳のせいなのか。
あと関係ないけど、「カンタービレ」という単語はなじみが薄いせいか、最初のうちは「のだめカンタビーレ」とか「のだめカンビターレ」とかとタイトルを誤解していた。
恥ずかしいので内緒にしておこうかとも思ったが、試しに「カンタビーレ」や「カンビターレ」でググッてみたら結構似たような間違いをしている人がいたので、安心して恥を晒すことにした。
働きマン
「監督不行届」のおかげで男性オタクの間でもすっかり名が知れ渡った、安野モヨコ先生のコミック。恋よりも女であることよりも仕事を優先して「働きマン」と化してしまう、大変に男らしい主人公の女性が大変に魅力的(人間として)。こういう女性と結婚したい! とか公言しちゃうから、自分は「椎名先生のマンガのファンって、やっぱり美神令子みたいな強い女性の尻に敷かれたいものなんですか?
」とか他の女性から言われてしまうんだなあと思った(マンガの感想とは関係ないコメント)。
それはともかく、このマンガはあくまで主人公を中心とした働く女性の視点で描かれているが、登場する男性陣もそれぞれ「仕事」に対して独特のポリシーとスタンスを持っており、誰もかれもがやたらと格好いい。読んでると仕事に頑張りたくなる効能があるので、仕事で気合いを入れたい人は男女問わず読むが良いです。
あと、このマンガの中に出てくる「男スイッチ」というフレーズにおける「男」は、セックスやジェンダーとしての男ではなく、もっと抽象的かつ概念的な意味での「男」であることに違いない。こういう表現をする場合に最も適した漢字はやっぱ「漢」なんだろうと思うが、でも安野モヨコのマンガで「漢」はどうか。案外格好いいのか。
電波男
みんな大好き「しろはた」の本田透氏が書き下ろした、現代社会におけるオタクが求める愛とは何か? を世間に訴えた話題作。
マンガじゃないですが、読んだのでせっかくだからちょっと触れます。
この本、本来なら不変であったはずの「愛」さえもが「金」と交換可能な資本となってしまった「恋愛資本主義」と著者が称する現代社会における哲学書としても読めるし、またそんな社会で「二次元」を愛するしかない境遇に立たされたオタク達に救済の道を指し示す宗教書としても読むことができるとても奥深い本なのだけど、基本的な位置付けとしてはやっぱり「負け犬の遠吠え」に代表される現代未婚女性特有の一方的な男性観に対する回答(というよりは強烈なカウンター)、と捉える社会学的なアプローチで読み解くのが妥当なのかなと思った。
本の主張からは相当先鋭化している印象を受けるが、Exciteブックスのインタビューを読めば、著者の主張は「異性にモテなくて妄想に逃げても別に悪いことじゃない、と思えば気楽になれるよ
」という点にあることが判る。そういう意味では、「いざとなったら死んじゃえば良い、と思えば気楽になれるよ
」と主張した「完全自殺マニュアル」みたいな位置付けにある本とも言える。多分。
そういう内容の本なので、どうしても語り出すととマジメになってしまいがちなんだけど、そんな中で「電波男と負け犬女の恋愛
」という視点から書かれた、「Beltorchicca」(demiさん運営)の4/1の日記にある『電波男』評がもの凄く面白かった。
ここまで電波男と負け犬女の恋愛に対するスタンスが開いてしまった今、果たして両者が歩み寄って愛し合えるだけの余地は残っているのか? 「電波男と負け犬女の恋愛」というテーゼは、今後の日本を支える世代でありながら将来に夢も希望も持つことができない、20~30代の男女が共有している心の問題をも象徴しているのではないか?
そんな気がしてきたぞ?(気のせいかも)
※私信:
今週は仕事が超忙しくなるので、しばらくの間は更新やコメントへの返信などの活動ができなくなります。スンマソ。
あと、Amazonアソシエイトやbk1ブリーダー経由でお買い物をして下さった方々に感謝。
2005/04/23
■シグルイ・イン・ライブラリー
『狂おしく 血のごとき 月はのぼれり
』
秘めおきし 魔剣 いずこぞや
伊良子清玄と藤木源之助が怪物となった夜。
月と、マリア様だけが二人を見ていた。
□
そんな感じで、「シグルイ」3巻が出てからというもの、再び「シグルイ」と「マリみて」をコラボレートする遊びが自分の脳内で再流行中の私ですが!(挨拶)
「シグルイ」2巻の時は、『物語の根底に「完成された封建制度の狂気」という共通したテーマがある』という視点から「シグルイ」「マリみて」双方の物語の類似性を指摘しましたが、先日発売された「シグルイ」3巻、およびマリみて新刊「イン・ライブラリー」の幕間劇『イン・ライブラリー』においても、やはり同様の傾向が見られると思います。
「シグルイ」3巻の内容は、虎眼の妾のいくに手を出したことで虎眼の怒りを買った伊良子清玄が仕置きされて廃人となる様を、それこそ最初から最後までみっちりねっとりと描写している訳なのですが、何故伊良子がここまでメタメタにやられちゃったかと言えば、妄想に囚われて後先が考えられない状態になっている道場主・岩本虎眼に対して常識的なツッコミを入れられる状態の者が誰も存在せず、虎眼の意のままに動いて伊良子をシメることしか考えられない「傀儡」と化していたからに他なりません。
むしろ突っ込むどころか、伊良子を除く全ての虎眼流剣士達が積極的に岩本虎眼の狂気の世界を受け入れて伊良子の仕置きに荷担しているところに、この作品が描いている狂気の本質があります。
3巻の「犠牲者」となった伊良子は元々狂気の道場の埒外に存在していた人物ですし、いくと三重の二人の女性は、自分を取り巻く絶望的な状況を変える力が彼にはあると思ったからこそ伊良子を愛するようになったと思うのですが、でも「シグルイ」を取り巻く世界は「少数のサディストと多数のマゾヒスト」を前提として成り立つ狂気の封建制度によって支配されています。制度を受け入れられない者は、制度によって葬り去られる運命にあるのです。それが封建社会というものなのです。
客観的に見れば、伊良子を何とかするよりも、あきらかにおかしい(頭が)虎眼を何とかした方がみんなハッピーになれるんじゃ? と突っ込みたくても、この作品世界のシステムは斯様な突っ込みを全く受け付けません。虎眼の狂気が全てを統べる閉塞環境の中であらゆる者がおかしくなっていく様を、我々はただ「うへぇー」と呻きながら見守るしかないのです。
つまり「シグルイ」とは、「封建制度」という作品世界の有り様がその作品の面白さを規定する、システマチックな面白さに溢れた作品と表現することができます。
□
「彼女。変わりました
」
松平瞳子は、はじめて細川可南子の笑みを見た。
□
そして「マリア様がみてる」も、また「作品世界の有り様がその作品の面白さを規定する、システマチックな面白さ」に溢れた作品です。カトリックの女子校という舞台設定もさることながら、「姉妹制度」という文字通りのシステム、そしてそのシステムがあるが故に生み出される人間関係の数々が、この作品世界の根底を形成しています。
特に「イン・ライブラリ-」に掲載されている、"名作"の誉れ高い『チョコレートコート』はまさにこれに当てはまるエピソードです。この話は、作品世界に「姉妹制度」が存在しなければ、そもそも物語として成立しません。姉妹制度が「契約」として婚姻にも似た強い力を持っているからこそ、「チョコレートコート」における三角関係は成り立つのです。
長期連載として安定した面白さを発揮している作品は、大抵はこの「システムが規定する面白さ」を持ち合わせているのではないか、と思われます。
□
「よく寝てよく食べてストレスはため込まない。
」
愚痴を言いたくなったら、私のところに来る、いい?
顎先をかすめただけの祐巳の言葉は、
それ故に瞳子の脳を十分に震盪せしめた。
□
更に「マリみて」の場合、「作品世界のシステムが、読者の常識的な突っ込みを全く受け付けない」という「シグルイ」同様の狂気的な要素も、同時に持ち合わせています。
それが顕著に表れているのが幕間劇「イン・ライブラリー」で、この話は要約すると「祐巳が寝てる間に居なくなった祥子さまをみんなが探す
」というただそれだけのお話であり、「別に生徒会総出で探さなくても、館で待ってりゃいいだけじゃん? そんなに一大事なのか?」と客観的に突っ込んでしまえばそれまでです。多分、これを読んだ人の半分以上は、心の中でそう思ったに違いありません(断言)。
しかし、前述したように「マリみて」世界には「姉妹制度」というシステムが存在しており、また主人公の福沢祐巳自身がその「姉妹制度」が原因で「誰を妹にすればいいのか」と悩んでいるという背景があるので、こんなお話でも
- 「大好きなお姉さまを捜す」という理由で、祐巳が校内を徘徊する理由ができる
- その祐巳の最有力妹候補である瞳子を登場させて祐巳と絡ませ、読者に興味を惹かせる
ことが、物語的に可能となります。もはや祐巳に対しては、こと姉妹問題のことが絡むと常識的な突っ込みは通用しないのです。
この辺、物語序盤で祐巳が山百合会の「埒外」な立場の視点から他のメンバーに常識的な突っ込みを入れていた頃と比べると、なかなか興味深いものがあります。これを「成長」と呼ぶのか「順応」と呼ぶのかは難しいところですが、祐巳もまた「マリみて」世界における狂気を体現する存在になったことだけは間違いないでしょう。狂気を維持する体制側の人間になるというのは、つまりはそういうことなのです。
虎眼流を踏み台にして己の野心を成就させようとした伊良子は「仕置き」によって剣士としての命脈を絶たれた一方、虎眼流のシステムの中で己を磨き続け、伊良子を叩き潰した藤木は「怪物」と化して行きました。
そして福沢祐巳もまた、リリアンにおける姉妹制度システムの中で徐々に「怪物」となりつつあります。もはや、彼女の誘いや説得に逆らえる者は、この作品世界の中では誰もいないのです。
□
文化祭劇の練習の日。ただ一人山百合会の命に背き、瞳子の誇りを守った者。
「あの方は傀儡(スール)どもとは違う。血の通うた誠の薔薇さま
」
寒い筈がない。乙女の胸の内に、福沢祐巳が燃えていた。
□
祐巳が藤木よりもタチが悪いところは、己がどれだけ強い存在なのか、当人がまったく自覚していないところにあります。
「祐巳さまが自分を訪ねてきた」と知らされた瞳子はすっかりその気になっちゃってるみたいですが、一方の祐巳は相変わらずそれに気付いていません。この二人の関係は非常にマンガチックで魅力的ではありますが、また非常に恐ろしくもあります。もし、この期に及んで祐巳が瞳子を妹にしなかったら、瞳子の今の気持ちはどうなってしまうのでしょうか? 同じく祐巳を慕っている可南子は?
祐巳が「妹」を決める段になった時、瞳子や可南子が「怪物」と化さないことを祈るのみであります。
□
■読んだマンガ報告041118
あかほりさとる対赤松健のあざといマンガバトル!
先週は赤松健の勝ち!(挨拶)
ついにあかほり原作マンガを投入ですよ。すごいなあ週刊少年マガジン。
マガジンは、いよいよ本格的にソッチ路線で行く決意を固めたのでしょうか。果たしてマガジンは、「しゅーまっは」とか「ななか6/17」とか「スクライド」が載っていた、覚悟を決めてた頃の週刊少年チャンピオンの姿を彷彿とさせる領域にまで到達することができるのでしょうか。
がんばって下さい(平坦な声で)。
□
そして、マガジンにおけるソッチ系路線の最右翼を担う「魔法先生ネギま!」8巻をこの前読んだのですが、
- 偉大な魔法使いであった父親に少しでも近付こうと健気に努力する、主人公の少年!
- その少年に隠された暗い過去が、ついに明らかに!
- 過去に主人公と因縁を持つ、強大な敵との再会! 怒りのあまり暴走する主人公!
- 戦いの中で育まれる、かつてのライバルとの友情! 友に励まされ、主人公は冷静ないつもの自分を取り戻す!
- 努力・友情・勝利! 主人公は過去を乗り越え、自分の進むべき道を見つけ出した!
- そして、成長した主人公の姿を遠くから見守るヒロインが静かに微笑んでエンド!
という、まるで普通の格闘マンガみたいなよくできたストーリーが展開されててビックリ。
お約束ながらも燃えるシチュエーションの連続っぷりに、自分の頭の中に住んでいる中学二年生要素はもう大喜びです。
お約束的な展開をキッチリこなして対象読者(この場合は男子中学生)を満足させるマンガを作ることができる氏の能力は、もうちょっと誉められても良いんじゃないかもと思うのですが、でも氏は絶対に自分のマンガを誉められないように美少女キャラの裸とかおっぱいムニュとかをそこかしこに配置させてカムフラージュを施し、「赤松健のマンガは相変わらずダメだなあ!
」という世論を形成する方向にあえて自らを誘導しているところに、先生のそこはかとない奥ゆかしさを感じます。
ええ、ええ、そりゃもう判ってますとも!(←誰ともなしに)
□
あと、同じく先週発売された「結界師」5巻も読みました。
この巻は、ウロ様の登場を契機に良守が「烏森の地」の秘密の奥深くにさらに踏み込み、またそれと同時に烏森を狙う新たなる敵も登場して来たという意味において、ストーリー的にはかなり重要な部分に位置するエピソードが掲載されているのですが、しかしそれ以上に大切だったと思ったのが
時音の祖母の時子さんは、若かった頃は相当のボインだった
という設定なのではないかと、私は思うのであります。
図らずも、この前のサンデーでは良守の祖父の繁守はボイン好きだったという事実が明らかにされましたが、これは間違いなく昔惚れていた時子さんのボインが原因ですよね。繁守も今後烏森を巡る争いに何らかの形で関わってくる可能性が高いことを考えると、これもまた今後何らかの伏線になって来たりしないのでしょうか。しないのでしょうね(自己完結)。
せいぜい、隔世遺伝の理論に基づいて時音がボインに成長するエピソードが増えるくらいでしょうか。
あと、百合奈が相変わらず激しくカワイイです。今後も、彼女が良守絡みで時音姉さんにつっかかる展開を激しく希望。この冬の「結界師」の同人シーンは、百合奈×時音がキますよ!(来ません)
以上、週末に読んだマンガ報告でした。
2005/04/12
■絶対可憐チルドレンが星雲賞コミック部門にノミネート
いきなり本題ですが、「絶対可憐チルドレン」が2005年星雲賞・コミック部門の『参考候補作品』に選ばれています。
ネットで感想を読んだりした範囲では、「絶チル」はSFファンの方から高い評価を得ているっぽい感触はあったんですけど、まさかSFファンによって選ばれる星雲賞にノミネートされるとまでは思っていませんでした。椎名作品は2000年にも「GS美神」が同様に参考候補作品に選ばれたことがありますけど、「絶チル」は「美神」と違ってあくまで短編作品ですからね。それだけ、SF者の心を震わせるモノが「絶チル」にはあったということなのでしょう。ファンとしても喜ばしい限りです。
やっぱり、みんな超能力少女が大好きなんだなあ(間違い)。
□
で、SFという観点では「絶チル」は他のノミネート作品と比べても十分対抗できるだけのスペックを持っていると思いますけど、この中で実際にどの作品が受賞するか? と予想するとすれば、個人的にはあえて「愛人 -AI・REN-」(田中ユタカ)を推したいところです。
この作品、最初のうちは『余命幾ばくもない主人公の少年・イクルが、彼に安らぎを与えるためだけに遺伝子操作によって作られた「愛人」・アイちゃんと、典型的な田中ユタカマンガみたいなラブラブな毎日を送る』――というマンガのはずだったんですが、次第に物語がスケールアップし、最終的には『人類という「生物種」とはいったい何なのか? 人として生きるというのは、どういうことなのか?
』と読者に問いかける、壮大なスケールの物語に成長。田中ユタカ氏が恋愛マンガ家としてのキャリアと才能を全て注ぎ込んだ、畏怖するべきレベルに到達したと言っても決して過言ではない傑作です。死ぬ前までにはみんな読んでおくべき。
あと、道原かつみ氏の「ジョーカー・シリーズ」が完結していたことを、星雲賞のノミネートで初めて知りました。この人のマンガはちゃんとSFとして面白いので、昔はよく読んでた記憶があります。「キャウ・キャット・キャン」がもう大好きで大好きで。15年くらい昔の話ですが(古すぎ)。
「絶チル」は、これらの作品とは違って「SF的なテーマは提示されているけど、物語として完結していない」というディスアドバンテージがあるのが辛いところかなと(「連載化を狙ったパイロット版」という構造上、話がこうなっているのは仕方ないですけど)。勿論、マンガとしては十分にオモロいんですけどね。
まあでも、「絶対可憐チルドレン」が正式連載になり、短編版で提示された「やさぐれ超能力少女の健全な育成」「超能力を『持てる者』と『持たざる者』の間にある葛藤」「定められた未来への挑戦」といったSF的な題材を描ききることができれば、星雲賞に再びノミネートされた挙げ句にコミック部門を受賞するのは確実な勢いですので、その時はぜひ! ということで一つ。
なんかよく判らない記事になってしまいました。
※私信:本職の方がアレな感じなので、しばらくの間は軽めの分量の記事を不定期に飛ばすことになりそうです
2005/04/09
■サンデーコミックス逆ランキング
ちょっと前のことですが、Amazonのアソシエイトプログラムに参加しました(いきなり)。
Amazonにある(自作のbk1プラグインではフォローできない、単行本以外の)商品の画像を合法的に使うのが主な目的です。例えばこんなの。
それでAmazonのアソシエイトを取って一度やってみたかったのが、逆ランキングです。Amazonで商品の一覧を表示させる時には様々な条件で並べ替えができますが、「売れている順」で並べた後、一番最後のページから逆に検索結果を辿ることによって「Amazon売れてないランキング」を作成することが可能なのです(陰険)。
以前、「魔法使いマールの冒険」のマールさんが『amazonで売れていない順のコミックランキング』というネタ(1/17)を公開されていたのですが、その時のランキングトップがワイド版「GS美神」の11巻だったという、このサイト的にはちょっと面白い見過ごせない結果が出ており、いつか自分でもやって結果を検証してやろうと思ってました。
ので、今やります。
□
方法:
Amazonの少年サンデーコミックスの一覧からAmazonランキングを頭から順に辿って逆ランキングを出力するプログラムを、(わざわざ)作成して実行。
Amazonに実際に在庫があるもの(発送期間が「通常~以内に発送」になっているもの)のみをランキング対象とする。
結果:
Amazonサンデーコミックス逆ランキング (05/04/09現在)
考察:
「MAJOR」「犬夜叉」といった、如何にも売れてそうなタイトルが出て来るのが面白いところです。実際、これらの商品の「Amazon.co.jp 売上ランキング」を調べてみると、やっぱりそれなりに売れているのが判ります。
Amazonの「売れている順」は、その商品の売り上げ総数ではなく、最近になって売れた商品の数量に基づいて決められているのではないか? と思われます。旬な商品が上に来る仕掛けですね。まあ当たり前と言えば当たり前ですが。
なんにしろ、ここに美神がいなくて良かったです。
ちなみに上位ランキングはこうなってました。
Amazonサンデーコミックス上位ランキング (05/04/09現在)
あの「ハヤテ」が、あだち・高橋・雷句といった並みいるメジャー作家の作品の更に上を行くAmazonはやっぱり凄いなあと思いました。
2005/03/09
■おたく:人格=空間=都市
今日はマンガとかあまり関係なく、普通の日記っぽいこと書きます(挨拶)。
週末に都内に出る用事があったので、せっかくだからということで恵比寿の東京都写真美術館でやってた「グローバルメディア2005 おたく:人格=空間=都市」展(以下、おたく展)を観てきました。ヴェネチアの国際建築展で公開されて好評を博した(らしい)展示を再現しました! という触れ込みのアレです。
会場には午後1時過ぎに着いたのですが、既にかなりの入場待ち行列が発生しており、実際に入場できるまでに1時間近くかかってしまいました。こんな行列作ってまで「おたく」的なモノをわざわざ見たいだなんて、みんなモノ好きなのだなあと思いました(人のこと言えませんが)。
展示内容は、ラジオ会館とかに置いてあるレンタルショーケースの再現、床に貼られたり天井から吊されたりしている色々なアニメの販促ポスター、様々なジャンルの同人誌の実物展示、コミケのサークルカットを実際の配置通りに展開してみた図、模型で表現した秋葉原の町並み。そんな感じ。
全体的に、いわゆる「おたく」的な、更に言えば「秋葉原」的なエッセンスを展覧会の会場に濃縮して見せてやろうという意図が感じられ、「海外の展覧会向けとはいえ、よくもここまでそれっぽいモノを集められたものだ
」と感心させられましたが、何しろ観客の数が多かったので、個々の展示物や会場全体の雰囲気をじっくり味わって鑑賞できる雰囲気ではなかったですね。
まあ、常に人で混雑しているのが秋葉原の特徴でもあるので、会場内で秋葉原同様の混雑を生み出す我々の存在も、また「おたく展」の展示物の中の一つなのだ! みたいなメタ的な意図があったのかも知れませんが(多分考えすぎ)。
そして今回の展示物のメインは、「趣都の誕生・萌える都市アキハバラ」で主張されている『秋葉原という街の今の形は、秋葉原に集う「おたく」の個室を巨大化させたものである』という「おたく:人格=空間=都市」論を具体化した「おたくの個室」と銘打った部屋なのですが、でも「この部屋に入るだけで更に1時間程待つことになりますが、よろしいですか?
」とか案内の人に言われたので、さすがに断念してしまいました。コミケでだってそんなに並んだこと滅多にないのに!(ダメ)
ヴェネチアならともかく、ここ東京では「おたくの部屋」なんてそれこそ普遍的に存在しているものだと思うのですが、それでもあえておたくの部屋を見たいだなんて、みんなモノ好きだなあと思いました(人のこと言えませんが)。
それでこの展示を我々が見る価値があるかどうかなのですが、基本的にこの展示で提示されているおたく的なフレーバーは、基本的には恵比寿から電車で30分くらいで行ける秋葉原の駅前にある秋葉原ラジオ会館に行けば得られるものばかりなので、少なくとも日本在住の現役おたくな皆様方なら、あえて行く必要性はないでしょう。秋葉原さいこう。
強いて言えば、「趣都の誕生」で述べられている理論が具体化した姿を見てみたい評論家気質の方、および身近におたくがいないけど「おたくの空間」というものがどんなものかを見てみたい物好きな方向けでしょうか。ただ、前述したように会場内は混雑が予想されるので、「おたくの個室」を実際に見たい方は長蛇の列を覚悟した方が良いです。
□
あと、(既に終わってしまいましたが)同じ東京都写真美術館で開催されていた文化庁メディア芸術祭も見てきました。
「マインドゲーム」が想像以上に変なアニメでビビったこと、「まかせてイルか!」が普通に面白そうだったので全部見てみたいなあと思ったこと、ニンテンドーDSの「ピクトチャット」が異様に面白いのでDS欲しいと発作的に思ったこと、「YKK AP EVOLUTION」の『海岸や線路の上を浮遊する空想物体』の格好良さにグッと来たこと、あと「夢」における夢オチの引っ繰り返しっぷりが印象に残りました。
以上、普通の日記でした。
2004/12/28
■丸川トモヒロ氏は若々しい椎名高志説
こちらは、私こと深沢が管理運営を行っている、椎名高志ファンホームページ C-WWW です(挨拶)。
いきなりですが、最近ニュースサイトで話題になっている「赤松健」論を書いていらっしゃる「ピアノ・ファイア」のいずみのさんの日記で椎名高志ネタがあったので、ブログっぽく反応。
丸川トモヒロ『成恵の世界』7巻
個人的に丸川トモヒロに付けているキャッチコピーは「椎名高志の後継者」。あるいは「若々しい椎名高志」。
んで椎名高志の原点にはるーみっくワールドが広がっているので、高橋留美子の孫にあたる漫画家だと思ってるんですが。同じ説を主張してる人はみかけないなあ。丸川さんがシイナをどう思っているのかは是非知りたいのだけど。
私自身は「成恵の世界」をそういう視点から意識して読んだことはありませんが、言われてみれば「ああ、なるほど」と納得できる意見だと思いました。
「成恵の世界」には、SF要素とほのぼのコメディ要素が高い次元でミックスされた「はじめてのおつきあい」や「ポケットナイト」などを代表とする作品を手がけていた、1990年代初頭のまだ若かった頃の椎名高志氏のマンガに相通じるモノを感じます。
現在の丸川トモヒロ氏の路線は、当時の椎名氏が将来取り得る「可能性」の一つだったのかも知れませんね。
でも、椎名氏はSFが好きなのと同じくらい「モンティパイソン」も「ヘルハウス」も「悪魔のいけにえ」も大好きな人なので、「成恵の世界」のようなハートウォームな物語だけを作って気が済むタイプの作家じゃないことは確かなのですが(笑)。
私は丸川トモヒロ氏のマンガは「成恵」しか知らないので、氏の中には成恵以外にどんな「引き出し」があるのか、ちょっと興味があります。何となくですが、いずみのさんが仰るところの「若々しい椎名高志」の代名詞に相応しいマンガを作ってくれそうな予感はしますね。
一度サンデー超増刊辺りで描いてくれないでしょうか(無理)。
あと、椎名高志といえばやはりロボ娘ですが、椎名氏はおそらく「成恵」に出てくる機族みたいな、人間と同じ思考能力や倫理観を持つタイプのロボ少女は自分のマンガには出さないのではないか、と思います。
氏の代表的なロボ少女として「GS美神極楽大作戦!!」のマリアを例にしますが、マリアは「人間の命令は理解するが、人間とはまったく違ったロジックで動いているが故にコミュニケーションにギャップが生じる
」ところに、マンガのキャラとしての面白さがあります。そして、それは椎名氏が考える「ロボットの魅力」の本質でもあるのです(この辺の椎名氏のロボに対する考え方は、SFオンラインのインタビュー記事に詳しい)。
一般社会で稼働するには明らかに致命的な欠点を抱えているロボット少女がいて、「それでもかわいい! 買う!
」と叫んでしまう男の子がいる。「椎名高志」的なマンガの面白さはそんなところにあるのかな、とか思いました。
おそらく椎名氏が「機族」をネタにマンガを作るとしたら、鈴ちゃんのようなキャラではなく、7巻に出てきた武伏みたいな「狂った」キャラを主役にするんじゃないかという気がします。
□
せっかくですので、「赤松健論」の簡単な感想を:
AI止ま編:
「AI止ま」というマンガが、赤松健という新人漫画家を如何に「少年漫画家」として成長させたのか――という軌跡が、判りやすくまとめられています。
週刊で連載開始→実力/人気不足でマガスペに降格→制作体制を強化して劇的に作画能力と脚本能力を向上→人気も急上昇→大円団で円満終了→「人気作家」として週刊復帰へ! とものすごい変化を経験した時期なので、漫画家としての赤松健を語る上では「AI止ま」が一番題材として面白いと思います。
ラブひな編:
ファンの間でこれほど「景太郎の瀬田化」が嫌われているだなんて知りませんでした。「景太郎の成長を(読者にとっても、成瀬川にとっても)極めて判りやすく表現したのがあのスタイルなのか」程度の認識だったので、そういう読み方もあるんだなと素直に感心。
個人的には、9巻で景太郎が成瀬川に告白した時点で、「ラブひな」の実質的な主人公は成瀬川に移ったと認識しています。9巻以降は、恋愛に対して幼稚なままのヒロインに成長を促す、成瀬川にとっての成長物語として「ラブひな」を読んでました。こういう読み方はどうだろう(と言われても)。
2004/12/07
■まったく容赦がないてれびくん1月号報告
「最強の術! ブラゴ・シェリ-大勝利!
」(挨拶)
2人の怒りのパワーでゾフィスを倒したぞ!
「てれびくん」のアニメ先取り情報は、相変わらず情報の要約っぷりに容赦がないですね。深沢です。
ようやく先月末に出た「てれびくん」を読めましたので、その情報を。
□
まず、このサイト的に最も重要な「ウルトラマンネクサス」のコミカライズ版ですが、今回は前回以上に子供に対して容赦がないなあと思いました。
原作の「ネクサス」が元々そういう話だからというのもありますが、掲載誌からイメージされる「幼稚」な部分は一切なく、原作の第5~8話におけるテーマの一つである「誰かを守りながら戦うことの難しさ
」を、簡潔な形ながらもキッチリと描写。自分を慕ってくれた女の子を戦争で失ってしまうという過去を持ち、今もその時の喪失感を抱えたままウルトラマンに変身して戦い続ける姫矢、そして今回の任務で女の子は救ったけど、その子から今回の事件に関する記憶そのものを消されてしまって一抹のむなしさを覚える狐門の心情が、ちゃんとマンガの中で描かれています。
また、原作の第5~8話は「ウルトラマンとダークファウストの闘い」と「怪獣が潜伏している廃工場に取り残された女の子の救出」の二つのストーリーがパラレルに進行するんですけど、そのシークエンスもできる限り誌面上で再現してやろうという心意気を感じる構成になっている点にも感心しました。「テレビシリーズのテイストを極力すくい上げて行く」基本方針は、今回も健在の模様です。
あと最後の1ページで、第8話終了の段階でこの作品世界が抱えている問題点を「誰かを――何かを守るって、難しくてつらいことなのかもしれない……
」という言葉で表現している(この場面は原作にはありません)シーンからは、難解に取られがちな「ネクサス」のストーリーの要点をまとめて作品の理解を助ける狙いがあるのではないかと思いました。
まあ、幼児向けの雑誌で「難しくてつらいことなのかもしれない
」なんて台詞が出てくることそのものが大変なことではあるんだけど(笑)。
そんな感じで、このマンガちょっと凄いです。掲載雑誌の対象読者が6歳以下という建前抜きで、あくまで「ネクサス」の持つフレーバーを余すところなくコミカライズしてやろう、という確たる目的を持ってマンガ作っている感じがします。
「てれびくん」を読みながら、『椎名高志って、こんな(色々な意味で)凄いことができる漫画家だったのか!』と今更ながら心底ビビってる私がいます。もうガクブル状態です。
前にも書いたように、おそらくこのマンガは多分コミックス化はされず(勿論されたら嬉しいです)、いわゆる「椎名高志マンガのファン」のほとんどはこのマンガを目にすることはないだろうと思われますが、そんな環境下でもちゃんと椎名先生は、己の仕事を遂行し続けています。この勢いがあれば、来年の「絶対可憐チルドレン」は相当期待できるモノになるんじゃないんでしょうか。ファンの皆さん安心して下さい(エラそう)。
作者のモチベーションを高めるための場を与えてくれた、という意味で、椎名氏に「ネクサス」のコミカライズを依頼した「てれびくん」の編集者の方に、我々ファンとは感謝するべきなのかも。
□
ついでに、「てれびくん」の他の記事で気になったのは、やっぱりみんな大好き「金色のガッシュベル!」のアニメ展開先取り情報。
「ゾフィスを倒したぞ!」という記事がこの段階で掲載されているということは、石版魔物編はいよいよ年内で終了すると解釈して良いのでしょうか。ということは、石版魔物編のラストでゾフィスがブラゴに心底ビビってガクブル状態になってしまう、あの伝説の萌えシーンがついにアニメで鑑賞できるということに。小心者っぷりをさらけ出し、ガクブルするゾフィス! 萌え萌えですな!(←萌えるのか?)
また、「てれびくん」の誌面では、シェリーがココと「再会」を果たして涙を流しながら抱擁する感動的なシーンのカットも掲載されていましたけど、やっぱりこのシーンは相当百合っぽくてエロいと思いました。「ネクサス」とは違う意味で子供に対して容赦がありません。楽しみです。
2004/10/24
■アッパーズはヤンマガを併合したということにしよう
今更な話になりますけど、「アッパーズ」最終号を入手しました。
椎名氏による「RED」のパロディも読みましたが、確かに妙にオモロいです。ちゃんと中身が「RED」になってるのが凄い。
さすが月刊OUT出身だけあって、この手のアニパロをやらせたら上手だなあと思いました(←30代未満には古過ぎて判ってもらえない褒め方)。
あと「アッパーズ」休刊に関しては、「本誌のヤングマガジンが不調なので合併させると言うのが本当の理由だそうです。
」(あにめ18禁・てんちょう日記10/18)という何だか説得力のある話を見つけ、ちょっと微妙な気分に。形としてはヤンマガにアッパーズの作品を持って行く、ということになってますが、ここまでヤンマガに移籍する作品が多い(最後通牒10/19)と、むしろヤンマガがアッパーズに併合されたと言っても誇張にならないんじゃないかという気がしてきました。
というか、ここまでしないといけない程、今のヤンマガはヤバい状況だというのにも驚きです。兄弟誌とはいえ上手く行ってるアッパーズを潰さなければならない英断を下すっていうのは、本誌の方はよっぽど(以下略)。週刊青年誌は全体的に厳しいみたいな話は聞きますけど、天下の講談社のヤンマガも例外ではなかったということなのでしょうか。
にしても、結果的に村枝賢一氏の連載マンガがヤンマガに載ることになろうとは、サンデーで「俺フィー」描いてた時代には想像すらできませんでした。
椎名氏とアッパーズ編集部の間には「戦友」と呼べる程の絆ができていることを考えると、事と場合によっては椎名高志氏のマンガがヤンマガに載る可能性すら出てきたということになるんでしょうか。これも「GS美神」とか描いてた時代からは想像することすらできない事態です。世の中何が起こるかわかりませんね。マンガ雑誌読みながら時代の変遷を感じる今日この頃。
2004/10/09
■蜘蛛巣姫感想
遅くなりましたが、ヤンマガアッパーズに掲載された「蜘蛛巣姫」の感想:
ちょっと前まではワガママなイケイケクソ女が主人公のマンガを描いてた椎名高志氏が、「男運に恵まれない独身女の悲哀
」を描ける程までに漫画家としても人間としても成熟したんだなあ、と何だか妙に嬉しくなってしまいました(←感想か?)。
何というかこう、とにかくヤツメがやたら可愛く思えてしまって仕方ありません。これくらいの年頃の女性の「男からカワイク見られたい」(けど、本性はやっぱり隠せない)心理がほどよく出ているところが特に良いです。2004年椎名高志マンガにおける嫁にしたい女性キャラナンバーワンの座に輝く勢いなステキっぷりです。
もちろん、そのヤツメをメロメロにする魅力を持った八郎太も良いですし、テンポ良く進むストーリーや、「生まれ変わる」というキーワードに統一されたテーマ、あちこちに散りばめられた椎名マンガらしい小ネタの数々も良かったのですが、やはりこのマンガの最大の魅力はヤツメに尽きますね。
愛しい八郎太の腕をかいがいしく縫ってるところも、彼に女がいると知って怪気炎を吐いてるところも、スパイダーマンっぽく城に乗り込むところも、密姫に一方的に嫉妬してるところも、八郎太に泣いてる姿を見られないように捨て台詞を吐いて立ち去るところも、もう全部カワイイ。
こういう女性をカワイイと感じてしまうということは、やっぱりオレも相応に歳をとったということなのでしょうか。
ああ、でも「喫茶・蜘蛛之巣」という煩悩丸出しなネーミングはどうかと思った。さすが蜘蛛女。
「パンドラ」の第3話を描いてからの椎名氏は、それ以前とは描くマンガの性質が変わってきている――というのが自分の今の椎名高志評なのですけど(いつかこの辺はちゃんと書いてみたいと思ってはいます)、「蜘蛛巣姫」もまたそれに連なるマンガの一つ。「絶チル」は、作者が結婚とか子育てとか連載切られたりとかいった公私に渡って様々な経験をして来たからこそ作れたマンガだと思いますが、「蜘蛛巣姫」もまた作者が様々なキャリアを経たから作れたタイプの作品のように思えます。
あと、なんか(「Time Slipping Beauty」の頃とは違って)作品全体に作者の余裕のようなものが感じられるような気がするのですがどうか。
□
それにしても、今回の「アッパーズ」はほとんど全ての作品が「終局」に向かって一斉に突っ走ってる感じがして、これはこれで妙に面白いですな(不謹慎)。袋とじ「G-taste」最終回なんか、最終ページのマスカレード男爵が格好良すぎてもう大変。こんなに「ご機嫌よう」の挨拶が似合う男だったとは!
ページの最後に「次回最終回」と書かれているマンガとそうじゃないマンガがあったんですけど、そういうマンガは後継雑誌かどこかに移転して続く可能性があると考えてよいのでしょうか。「RED」や「シュガー」の今後が気になります。「やまとの羽根」は終わっちゃうみたいで超残念。
2004/06/29
■シグルイ2巻
「封建社会の完成形は、
」
少数の祥子さまと多数の祐巳によって構成されるのだ
そんな感じで、「シグルイ」と「マリア様がみてる」を無理矢理コラボレートする遊びがマイブームな私ですがどうですか(いきなり)。
「シグルイ」と「マリみて」は全然関連性がないように思われますが、実は双方の作品には「上下関係が厳格に定められた、極めて封建的な世界を作品の舞台にしている」「ほとんど全ての登場人物が『体制の維持こそが絶対である』という思想に支配されている」「体制維持のための象徴的な儀式がある」などの共通点があります。
つまり、どちらも極度に保守的・封建的な社会システムが作品の根幹をなしている、ということができるのです。
「シグルイ」とは、『真剣御前試合』を象徴に完成された封建制度の狂気の中で必死で生き抜こうとする侍達の生き様を描いた凄惨なドラマでありますが、「マリみて」もまた「ロザリオの授受」を象徴とした『姉妹の契り』という完成された封建制度の狂気の中で必死で生き抜こうとする少女達の生き様を描いた学園コメディである! と表現することができるのです。多分。
「入学した時から嫌というほど見てきた。
」
姉の仰せとあらば、意志をなくした傀儡(くぐつ)となる妹たち
「シグルイ」の2巻では、藤木源之助と伊良子清玄の両名による虎眼流の跡目争いが混迷の度を深める様子が描かれていますが、「マリみて」も現在は松平瞳子と細川可南子による祐巳さまの妹の座を巡る争いが激化しつつあります。
家康を輩出し、江戸幕府の封建制度を支えた松平家と、遠く足利時代に室町幕府の管領として権力を振るった細川家。奇しくも日本の封建時代を代表する名門の名字を冠された二人は、姉妹システムという名の封建制度の中で「祐巳さまの妹」「山百合会幹部」という、システム内での絶対権力の地位を目指して争う人物のネーミングとしては最適なのではないのでしょうか。
リリアン女学園における絶対権力者である小笠原祥子とも関係があり、生まれながらにシステムに馴染んできた生粋のお嬢様である瞳子か、あるいはシステムをも超越しかねない勢いで暴走する突進力を持った可南子か。いずれは冒頭に出てきた『真剣御前試合』に繋がるであろう「シグルイ」の今後の展開も気になりますが、「マリみて」の今後も同じように気になります。アニメ版の再開も楽しみです。
不屈の精神を持った乙女は、己に与えられた過酷な運命こそ、かえってその若い闘魂を揺さぶるものなのです。多分。
「細川可南子は妹(スール)ではない。
」
もっとおぞましい何かだ
□
…「シグルイ」2巻の感想を簡単に書こうとしたつもりだったのですが、どうしてこんな文章に?
今ちょっと風邪引いて熱が出てるせいにしていいですか?(と言われても)
とにかく「シグルイ」は面白いです。封建制度というシステムが内包している狂気を題材にした、まさに残酷無惨な時代劇コミックの傑作。作者の山口貴由氏は圧倒的に緻密な肉体描写と独特の言語センスで一世を風靡した「覚悟のススメ」で有名ですが、「シグルイ」は「覚悟」以上に氏の才能が冴え渡っていると思います。「シグルイ」は、間違いなく山口貴由氏以外には絶対に描くことができない、独特の魅力を持った作品です。
まあ、「覚悟のススメ」のファンの中で「シグルイ」を読んでいない人がいるとはとても思えないので今更なのですが、どうしても何か読んだ感想を書きたくてこんなエントリを起こしてしまいました。やっぱり、ちょっと熱に浮かされているのかも。
椎名高志ファンホームページへようこそ(挨拶)。
2004/06/23
■光の赤松、闇の久米田
突然ですが、「ネギま!」なら誰?(挨拶)
私は朝倉和美さんがお気に入りです。雑多な人間関係が入り乱れる学園生活の中で、独自の客観的な視点を保ちながらも積極的にクラスの中で立ち振る舞うことができる彼女のスタイルは、不器用だった学生時代の私が憧れていた生き方に近いものがあります。同様の理由で、「マリみて」の蔦子さんも好きですね。
まあ勿論、嫁にするなら本屋ちゃんで決まりな訳ですが!
そんな感じで(?)、先週発売された「魔法先生ネギま!」の6巻が異様に面白いです。
「お嬢様とボディーガード」の立場から大きく変化し始める木乃香と刹那の関係を物語の軸に据えた上で、ノンストップかつ高密度で繰り広げられるアクションシーンの数々やら、ネギ達の窮地を察して次々と駆けつけるクラスメート達の大活躍っぷりやら、強力なライバルに対して知恵と勇気で乗り越えようと頑張るネギ少年の雄志やら、凝りに凝った魔法や呪術の描写やら(特にクライマックスにおけるエヴァンジェリンは圧巻)と、最初から最後まで盛りだくさんの内容で心底楽しめました。
私は通勤電車の中で読んでいたのですが、あまりに集中し過ぎて思わず乗り過ごすところでした(バカ)。
勿論、これは赤松健先生のマンガなので、おっぱいぽいんとか風呂場でぽいんとかパンストでガン=カタとかそういうサービスシーンも過剰ですし、基本的にやってることはこの手のドラマのお約束に沿ったものなので物語的な目新しさは薄く、別にこれを読んだからといっても頭が良くなるとか人生にとってプラスになるとかそういう要素もあまりないんですけど、でも徹底的にエンターテイメントに徹した作品の作り方には好感が持てます。読んでるだけで楽しく、かつ元気になれる作品であることは確かです。
あと、要所要所で魔法や呪術の解説を入れ、ソッチ方面への知識欲をかき立てる誌面構成も上手いなと思いました。このマンガのメインターゲットである現役のオタクな中高生男子は、マンガの中に出てくる女の子と同じくらい、オカルトっぽいネタが大好きですからね!
つうか、もし私が現役の中学生や高校生だったら、このマンガに心底惚れ込んでいたんじゃないかと思います! あぶないあぶない!(手遅れ?)
それにしても、赤松氏は「ラブひな」の頃と比べても、エンターテナーとしての実力が遙かに上がっているような気がします。正直、「ラブひな」が一番面白かったのは4~7巻くらいまでだったんですけど(笑)、「ネギま」は面白さに底が見えません。なんか来年辺りにアニメになるとかいう噂も聞きますし、まだまだ楽しめそう。
この調子で行けば、CLAMP大先生に比類する(あるいは凌駕する?)メディアミックス作家として大成する日も、そう遠いことではないでしょう。そういう意味でもこのマンガには期待してます。
□
そして赤松健先生といえば久米田康治先生なんですけど、いくつかのブログで『「かってに改蔵」が次巻で打ち切りになる
』みたいなコメントを見かけたので、ちょっと不思議に思ってコミックス25巻を確認してみたところ、表紙カバーの折り返し部分には確かに「次号『かってに改蔵』最終巻は…
」なんて一文が。あー
それを踏まえてコミックス25巻の作者コメント「今巻の反省文」を読み直してみると、まあ確かにいつにも増してネガティブな雰囲気な文章書かれてますね先生。このコメントを真に受けた読者から心配されるのも判るような気がします。
こんなに心配してもらえるなんて、ホント先生はみんなから愛されてるなと思います。
ただ私の場合、ネットでもコミックスでもやたらネガティブかつ自虐的なコメントを出すのが久米田先生の芸風だと認識しているので、今回の反省文を読み、『最終巻』という単語を見ても、「今回はいつにも増して先生が絶好調だなあ!
」とか思いつつニヤニヤしてしまいましたが(ダメ)。『最終巻』という言葉も先生のいつものネタの一環なんじゃないかと思って軽く流してしまうような、そんな心境です。
個人的には、「改蔵」ってのは本来そういうスタンスで楽しむべきマンガでは? という認識なのですが、でもそれは私がどっか人として大切な何かを間違えてしまっているからなのか。
でも、もし仮に次巻で最終回となると、実質的にあと1~2話程度で連載を終わらせてしまわないといけない計算になるのですが、その程度の話数でこのマンガの物語を収束することは、果たして可能なのでしょうか。
ああ、なんか「かってに改蔵」を読むのが怖い。「からくりサーカス」で怖がってる場合じゃなくなって来ました。
2004/06/15
■全裸カタツムリはエロいな(感想)
そして、今日発売のアッパーズに載ってた、椎名センセのイラストを見ましたよ!
カッパ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!
いやまあ、イラストのテーマが「塗れちゃう寝姿
」なのでキャラ選択は間違ってはいませんし、前回の伊号ちゃんの時の「身体のパーツ取れ萌え」みたいな特殊極まりない萌え要素を必要としないことを考えれば遙かに難易度低くてユーザーフレンドリーなのですが(人外萌え程度ならみんなとっくに乗り越えてます)、でも何故ここでずぶ濡れ水着少女とかそういうものではなく、あえて河童を投入してしまうのか。これが椎名高志なのか(椎名高志です)。
やっぱり、どうしても必要以上に面白くしないと気が済まない人なんだなと思いました。
今回のイラスト集は、エロいという観点ではやっぱり吉崎観音氏のイラストが一番だと思います。
でもあれ痛そうだ(おっぱいが)。
□
この号のアッパーズでは、「バジリスク」がついに完結。壮絶かつもの悲しいラストシーンが印象的でした。
同じく「THE 大市民」は、主人公の山形氏の話を適当に聞き流してあしらってる女性の大人な態度が印象的でした(まちがい)。
2004/06/09
■コミック感想「夜の童話」
いきなりですが、7月からアニメ版「マリア様がみてる」の新シリーズ(自分内名称:マリア様がみてる~セカンドインパクト~)が始まるそうですね。
私は性格が曲がった女性キャラが大好きなので、今回から新キャラとして登場する生粋のトラブルメーカー・松平瞳子にはかなり期待してます。視聴者から『何このドリル女! 超ムカツク!
』とウザがられればこのアニメは大成功なんですよ! と制作スタッフが胸を張って豪語するくらいの暴れっぷりを期待したい所存。
基本的に「金色のガッシュ!」のパティみたいな役回りですしねこの娘(変な例え)。
□
で、それとはあまり関係なく、最近紺野キタ先生のコミックスを三冊(「夜の童話」「Cotton」「乙女は祈る」)まとめて購入してから、今ちょっと自分の中で紺野キタ作品がブームです。
"紺野キタ"と言えば、個人的には「ひみつの階段」を代表とする女学院寄宿舎ファンタジーを描く人、というイメージが強いのですが、これらのコミックスに収録されている作品の多くは、ちょっとそれとはフレーバーが異なっています。これらの作品も広義で言えばファンタジーの部類に入るんですけど、「ひみつの階段」のようなティーンエイジ向けではなく、より対象年齢の高い、文字通りの「大人の童話」といった趣を感じます。
その傾向が一番よく出ていると感じたのが「夜の童話」。作者が同人誌で発表した作品を集めたというだけあって、どの作品も深い(あるいは重い)メッセージ性を持っていると思います。
例えば、この中に収録されている「春を待つ家」という作品では、気ままに放浪の生活を送る社会性皆無な童話作家を父に持つ主人公の少女が、「いつかは離婚した母と同じように、そんな父を自分は排除するようになるだろう
」と心の底では予兆を感じながらも、それでも父の生み出す童話と、童話を作り続ける父を愛してやまない様子を、爽やかに描いています。
「ファンタジー」に生きる父と、その父を支えながら「リアル」の世界を生きる重さに耐えられなかった母。リアルな世界でファンタジーに想いを馳せることへの厳しさ。そんなことを考えさせられる作品です。
その一方で、逆に生活に疲れた中年のおじさんが「少女の姿をした、自分の『初恋』の化身
」なるポエジック極まりない存在と出会うという、ファンタジーをある種の「救い」として描いている物語があったりするのも、また興味深いところ。『夜の童話』というタイトルに込められた作者のファンタジーに対するスタンスや思い入れが伺える、興味深い作品集だと思いました。
とりあえず、「ひみつの階段」の世界観がオッケーな方なら、ファンタジーとは無縁な人生を送っている男性でも十分イケると思います。「百合姉妹」で紺野キタ先生を知ったとかいうような、そういう傾向がある方にもお勧めできそう。
――以上、bk1のトラックバック書評向けに耐えうるエントリを書いてみたつもりでしたが、書き出しが全然関係ない「マリみて」なのはどうかと思った。
2004/06/05
■講談社刊の青年漫画誌「ヤングマガジン アッパーズ」が10月に休刊
「マジですかー!」と、職場で叫びそうになりました。アッパーズって「バジリスク」を筆頭に(部数は少なくても)割と手堅く売っている雑誌というイメージがあったので、ここで休刊ってのはちょっと意外です。
「最後通牒」に掲載されている記事には「新ジャンルのコミック誌の創刊を決めた
」とかいうコメントが掲載されていますが、やっぱり講談社の方針変更か何かがあったのか?
というか、10月って椎名先生が「アッパーズ」で読み切りを載せる予定の時期と被っている気がするのですが!
ちょっと心配になってきました。
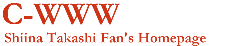
![宇宙船 05月号 [雑誌]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B00080K4S0.09.MZZZZZZZ.jpg)
